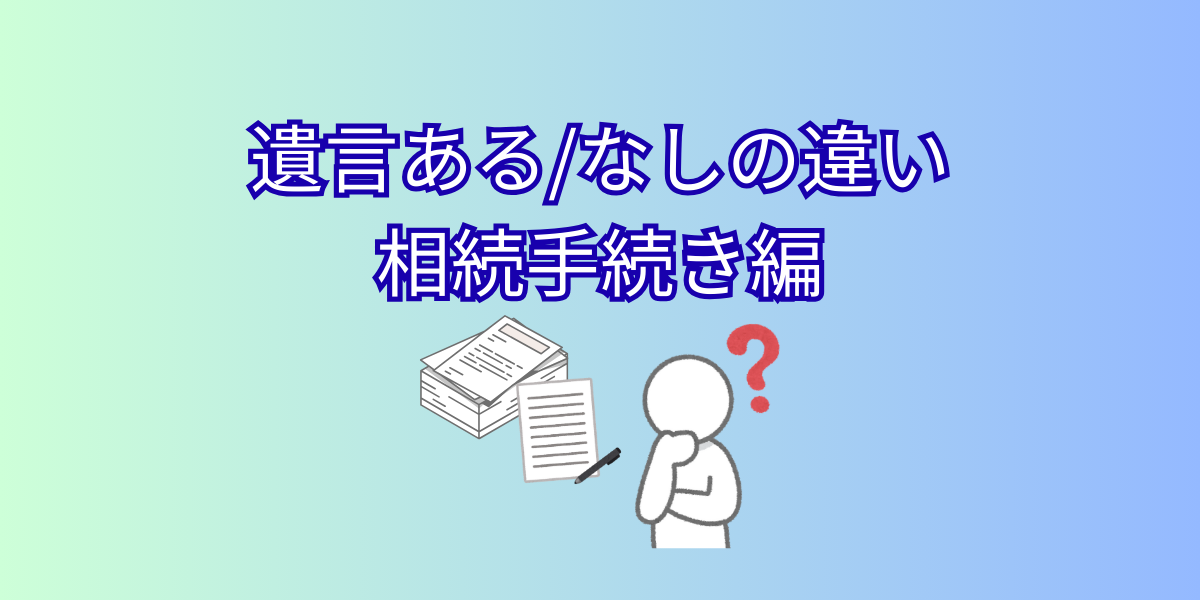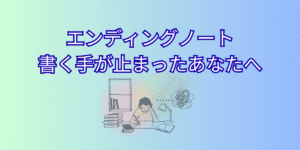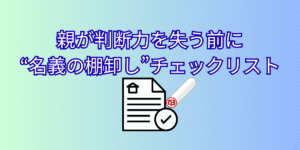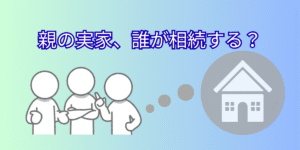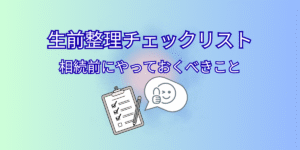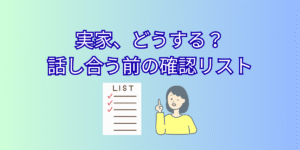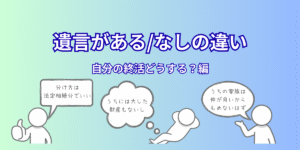何から始めればいい?──遺言があるかないかで、検認の要否や必要書類、かかる期間・費用は異なります。まずは早見表とフロー一覧でどのようなルートを辿るのかを把握しましょう。
| 1.公正証書遺言あり | 2.自筆証書遺言あり | 3.遺言なし→遺産分割協議 | |
|---|---|---|---|
| 最初にやること | 遺言執行者が手続き準備 | 家庭裁判所へ検認申立 ※法務局保管の場合不要 | 相続人確定→遺産分割協議 |
| 主導者 | 遺言執行者 | 遺言執行者 | 相続人全員(代表者) |
| 主な必要書類 | 遺言+戸籍類 | 遺言+戸籍類+検認関係 | 戸籍類+遺産分割協議書 |
| 期間目安 | 1〜2ヶ月 (財産内容次第) | 1〜3ヶ月 (財産内容次第+検認の分) | 1〜3ヶ月 (合意形成次第) |
| つまずきやすい点 or 注意すべき点 | 財産洗い出し不足による漏れ | 表現不備・検認待ち | 相続人全員の合意形成 |
<手続きまでの流れ>
1.公正証書遺言or 法務局保管の自筆証書遺言
遺言執行 → 名義変更
2.自筆証書遺言
発見 → 家庭裁判所へ提出・検認申立(法廷で開封) → 検認 → 遺言執行 → 名義変更
3.遺言なし
相続人確定(戸籍取得) → 相続人全員の合意形成 → 遺産分割協議書作成(署名捺印) → 名義変更
 終活ナビ子
終活ナビ子遺言があることで、相続人の負担が(時間的負担のみならず心的負担も)大きく軽減されることがイメージできるかと思います。
なぜ遺言が必要?遺言書の有無で変わる相続手続き
「うちは遺言なんていらない」と考えられているかたは少なくありません。よくある理由は以下の3つです。
- 財産が少ないから、わざわざ書くほどでもない
- 子どもたちは仲が良く、揉めることはないから
- お金をかけてまで作るのはもったいない
けれど、このような考え方には大きな誤解が含まれていることも多いのです。
| ❌ よくある思い込み | ✅ 実際はこうです |
|---|---|
| うちは財産が少ないから不要 | 遺言は財産が多い人だけのものではない |
| うちの子どもたちは仲が良いから大丈夫 | 表面上は揉めていなくても、不公平感に悩み、実は納得していないケースも多い |
| わざわざお金をかけるのがもったいない | 相続人に判断の負担と手続きのコスト・時間を先送りしているだけ |
実はこれ、相続・終活相談の現場で本当によく見かけるパターンです。また、事情をお聞きしたうえで「あなたのケースは絶対に遺言を残しておくべき。残された家族が、相続手続きでとても困ることになる可能性が高いですよ。」と強くおすすめすることもあります。本記事では、遺言書の有無によって相続手続きがどう変わるのか、その違いや注意点を、実例を交えながらわかりやすく解説していきます。
よく選ばれている2種類の遺言書
まず、ひとくちに遺言といってもいくつか種類があることを知っておく必要があります。実務上よく使われるのは自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。その違いについて、以下に簡単にまとめました。
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 自分で全文を書く | 公証人が聞き取り+作成 |
| 作成費用 | ほぼ無料(用紙代・保管料程度) | 有料(財産額に応じて数万円〜) |
| 保管 | 自宅 or 法務局(任意) | 原本は公証役場で保管 |
| 検認の有無 | 必要(家庭裁判所へ申立て) | 不要(すぐに手続き可) |
| 無効になるリスク | 高い(内容の不備が多い) | 低い(専門家が作成) |
| メリット | 手軽・費用がかからない | 確実・安全・手続きがスムーズ |
| デメリット | 検認・保管リスク・内容不備の可能性 | 作成に費用・時間がかかる |
※法務局の保管制度は“形式面の外形確認”に限られ、有効性の保証手続ではありません(詳しくは本文の説明へ)
実務で大きな違いとなる「有効性」のリスク
「公正証書と同様の効力を持つなら、自筆遺言の方が費用もかからなくていいのでは?」
そのように思われる方は少なくありません。しかし、実務上は公正証書との違いが非常に大きいポイントがあります。特に大きな差が出るのが、遺言の“有効性”が問われた場合です。
また、銀行などの現場でも、自筆証書遺言の提示ではすぐに相続手続きに進めないケースも多くあります。
「自筆遺言を持参されても、内容や形式を本部で確認する必要があります。 結果的に“遺産分割協議書”の提出をお願いすることになる例も少なくありません」──元銀行員
このように、自筆証書遺言は確かに「手軽さ」はありますが、 肝心の相続手続きの場面で“使えるかどうか”を考えると、大きな不確実性が伴うことは知っておくべきです。
📌この記事でわかること
- 遺言書が「ある」「ない」で、相続手続きや必要書類はどう違うのか
- 公正証書遺言と自筆証書遺言で、家族の負担にどんな差が出るのか
- 相続コンシェルジュが「必ず遺言を作ってほしい」と伝える具体的なパターンとその理由
遺言書が「ある場合」の相続手続き
遺言書がある場合、基本的にはそこに書かれた内容に沿って相続手続きを進めることになります。ただし、形式や保管の方法によって必要な対応が違うので注意が必要です。先ほど紹介をした主要な2種類(自筆証書遺言と公正証書遺言)の場合をそれぞれみていきましょう。
①「検認」が必要なケース/不要なケース
家庭裁判所での「検認手続き」については、以下の3パターンがあります。
- 自筆証書遺言を自宅等で保管していた→家庭裁判所で「検認手続き」が必要
- 自筆遺言保管制度を利用して法務局に保管していた→「検認手続き」不要
- 公正証書遺言を作成していた→「検認手続き」不要
自筆証書遺言の検認──よくある誤解
ところで、この法務局での保管制度や、裁判所での検認手続きについて、勘違いしている方が結構多いように思います。これらはどちらも遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
これは、制度が開始したことで注目を集めた自筆証書遺言書保管制度もまた同様です。
だから、自筆証書遺言で手続きを進めようとしても、「表現が曖昧」などの理由で銀行がすんなりと受け付けてくれないということも十分あり得る、というわけです。
② 遺言書が「ある場合」の必要書類の例(※財産の種類によって異なります)
- 遺言書(公正証書遺言の場合は正本)
- 被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡)
- 相続人の戸籍謄本・印鑑証明書
- 財産ごとの手続き書類(例:不動産登記、銀行名義変更など)
まず、遺言があるということは、亡くなった方があらかじめ財産の分け方を指定しているということ。そのため、基本的には相続人全員から遺産分割協議書への署名捺印を集める、というプロセスが不要です。
遺言書が「ない場合」の相続手続き
これに対して、遺言がない場合は、まず相続人全員による「遺産分割協議(=どのように分けるかの話し合い)」が必要です。
① 誰が相続人か確認する
- 戸籍を出生から死亡までさかのぼって取得
- 亡くなられた方に離婚再婚歴がある場合や音信不通の相続人がいる場合、調査に時間と手間がかかることも
② 相続人全員の合意が必要
- 遺産分割協議書の作成
- 相続人の署名・押印(実印)+印鑑登録証明書
③ 必要書類(例※財産の種類によって異なります)
- 被相続人の戸籍(出生〜死亡まで)
- 相続人全員の戸籍・印鑑登録証明書
- 遺産分割協議書
- 財産ごとに指定される必要書類 例:不動産登記簿謄本、銀行指定書類など(財産の種類によって異なります)
遺言があれば不要だった、相続人全員の戸籍や印鑑証明を集めたり、遺産分割協議書を作って相続人全員が署名捺印をすることが必要になります。
【比較表】実際に手続きするなら、どれがラク?費用は?
それでは、おさらいとしてそれぞれのメリット・デメリットをまとめてみてみましょう。
| 項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 遺言なし(遺産分割協議) |
|---|---|---|---|
| 相続手続のスピード | ◎ 検認不要で即使用可能 | △ 家庭裁判所で検認必要 | △ 相続人調査と遺産分割協議から開始 |
| 相続発生後の手続き | ◎ 遺言に沿って各手続きを進行できる | △ 遺言に沿った手続きがスムーズに進まないことも | × 遺産分割協議書の作成 が必須 |
| 相続人間の話し合い | ◎ 基本不要 | △ 基本不要 (ただし内容不備時は 協議が必要) | × 必須(全員の合意が必要) |
| 書類集めの手間 | ◎ 少ない (公正証書+戸籍類) | △ 中程度 (検認+戸籍類) | × 多い(協議書のほか 全員の戸籍・印鑑証明) |
| トラブルの起こりやすさ | ◎ リスクは最も低い | ◯ 内容不備で揉めることも | × 意見対立でトラブルに発展しやすい |
| 費用の目安 | △ 遺言作成費用数万円〜数十万円 | ◎ 遺言作成費用0円〜 (保管制度あり) | △ 相続発生後、書類作成や手続き代行で費用がかかる場合も…… |
| 有効性の判断 | ◎ 公証人が確認して作成 → 高信頼性 | △ 書き方に不備があると 無効の可能性 | × 法定相続人以外への 遺贈などはできない |
💡ポイント
遺言を残す皆さんは、ご自身との関係性、相続人同士の関係性やそれぞれの事情などに配慮して、大切な人に嫌な思いをさせないようにどうするのがベストか、と頭を悩ませます。もし、遺言がなかった場合、相続人が代わりに頭を悩ませることになります。
- 公正証書遺言が「最も確実」だが費用はかかる
- 遺言を作成する場合は、作成する人に費用がかかり、遺言を作成しなければ相続人に費用がかかる
- 自筆証書遺言はコスト面では優しいがリスク管理が必要
- 遺言がない場合は手間と時間が最大級に増す
こんな人には「遺言書」があった方がいい
- 相続人同士の仲が微妙
- 家族の構成が複雑(離婚・再婚・内縁関係など)
- 不動産や預貯金の分け方に偏りがある
- 特定の人に財産を残したい意思がある
「相続人同士の中が微妙」や「家族構成が複雑」のいろいろなパターン
明らかに仲が悪いという場合は言わずもがなですが、「仲が微妙」というのも結構くせ者です。相続・終活相談の現場でよく見られるパターンをいくつかあげておきます。当てはまる場合は、残される家族のために行動することをおすすめします。
- 子どものいない夫婦など、義兄弟や配偶者の甥姪が相続人となる場合
→人によってはほとんど話したことがないというようなことも……。 - 海外居住の相続人や居所不明の相続人がいる
→「長男は若い頃家を出ていき、何十年も音信不通」のようなケースも意外とよく遭遇します。 - 再婚者で「前妻との間の子たちとは離婚後一度も会ってない」というような場合
→再婚した今の奥様に、その子たちと連絡を取って遺産分割協議書を作る仕事をさせるのは酷な話ではないでしょうか?
遺産の中に不動産がある場合
不動産は、思っているよりも扱いが難しい財産です。というのも、「この家はいくらの価値がある」と言っても、それは売却してみるまでは本当にはわからないからです。実際の金額が見えにくい分、家族の間で意見が食い違いやすくなるリスクもあります。
- 介護と同居をめぐる「評価のズレ」
親と同居していた子が「長年、介護を一手に担ってきた」と主張する一方で、他のきょうだいは「親に生活費を出してもらっていただけ」と受け止めている……こうした“評価のズレ”は、不動産の相続をめぐってよく見られる火種です。 - 思ったほど「資産」ではないことも
親が残してくれた立派な戸建ても、相続が発生する頃には築30〜40年が経過していることも珍しくありません。固定資産税や修繕費、冷暖房効率の悪さなど、住み続けるにも、貸すにも、意外とコストがかかるものです。 - 収益不動産=「儲かる不動産」とは限らない
「お金を生む不動産」と聞くと一見魅力的ですが、築古のアパートや空室の多い物件だと、管理の手間と費用がかかり、実際の収支はトントンということも。建て替えが必要になるケースでは、かえって大きな出費や揉めごとの原因になることもあります。
まとめ
相続をめぐる手続きは、突然やってくることも少なくありません。だからこそ、元気なうちに備えておくことが、家族への最大の思いやりになるのです。遺言書があることで、手続きがスムーズになるだけでなく、家族間の無用なトラブルを避けることができます。ついつい「まだ元気だから」と、先延ばしにしがちな遺言。しかし、残された家族にとっては、あるかないかで負担がまったく違うものです。
もちろん遺言を書く/書かないは本人の意思によります。ですから、親に「遺言を書かせる」ことはできません。が、対話の余地がある親子関係なのであれば、子から親へ提案してみるのも良いでしょう。まずは、信頼できる情報源や専門家の力を借りながら、準備を始めてみてはいかがでしょうか。