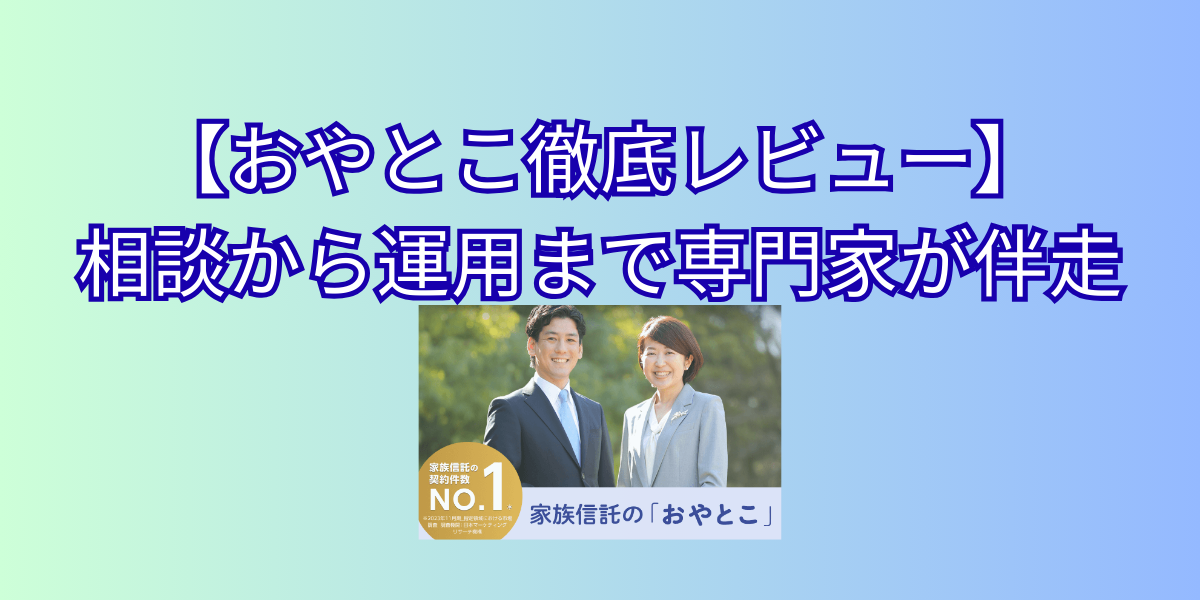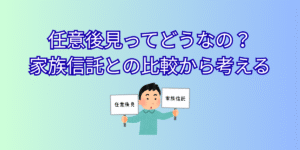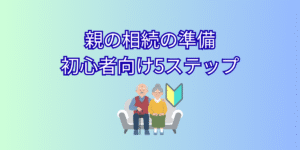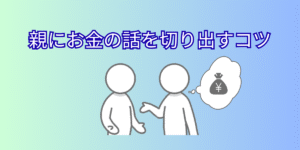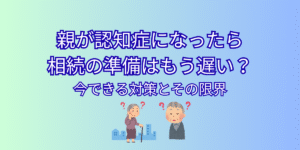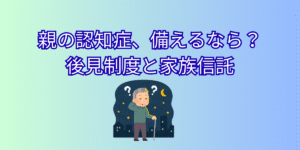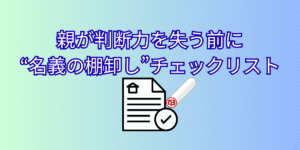本記事では、家族信託のおやとこ レビュー 評判 費用を中立に整理し、できること/できないこと、向いている人/向いていない人など、申込前にチェックすべきポイントをまとめました。
(※本記事は一般的情報です。個別ケースや最新の条件等は公式サイトや無料個別相談会でご確認ください。)
サービス内容:認知症による資産凍結への備えとして、家族信託の設計・運用を専門家+アプリで支援
料金の目安:初期5万円〜、月額2,480円〜、詳細は公式プランを確認
口コミ状況:ネット上の一般口コミは少なめ、一次情報は公式の事例・インタビュー中心
※広告を含みます。条件・料金は必ず公式で確認してください。
「おやとこ」とは?評判は?
おやとこは「親の資産凍結リスク」への備えに、家族信託を安全・便利に使えるよう設計された支援サービスです。
・相談→契約→運用まで、専門家が伴走
・契約発効後は独自アプリにより、財産管理の現状把握も簡単
・料金は初期費用(コンサルティング料+実費)と月額費用 ※内容により変動(後述)
新しいサービスであり、しかも家族信託という極めて個人的な情報を扱う性質上、一般には口コミが出回りにくい傾向があります。そのため「気になるけれど最初の一歩が踏み出せない」という方も少なくないでしょう。
一方で、公式資料には契約者から寄せられたコメントが掲載されており、コンサルタントへの信頼感や独自アプリの使いやすさについて高い評価が見られます。
運営体制とガバナンス
「おやとこ」を運営するトリニティ・テクノロジーは2020年設立のエイジテック企業。
代表の磨 和寛氏自身、司法書士の資格を持ち、士業グループの運営を経て現職に就きました。全国に14拠点を構え、家族信託分野での支援を展開。サービスサイトでは家族信託の契約件数で2年連続No.1(日本マーケティングリサーチ機構調査)と公表しています。直近は三菱UFJ信託銀行や東京スター銀行との業務提携など、金融機関連携も拡大しています。(出典は下記会社概要のボックスをご覧ください。)
 終活ナビ子
終活ナビ子家族信託の契約件数も多く、専門家向けコンテンツの提供も広げるなど、この分野を先導する存在。制度が新しいために専門家の人口が限られるこの領域で、「場数」を重ねていることは、利用者側の安心材料と言えるでしょう。
できること/できないこと
そもそも家族信託でカバーできることとできないこともありますし、「おやとこ」でサポートされていることとされていないこともありますので、念のため確認しておきましょう。
| 項目 | できること | できないこと or 要注意事項 |
| 家族信託の設計 | 家族構成・目的に沿った設計提案 | 医療・身上監護の代理は家族信託の範囲外(任意後見の領域) |
| 契約の作成支援 | 契約書作成の支援/公正証書化の手配支援 | 公証人費用など実費は別。個別見積もりが必要。 |
| 運用サポート | 口座・取引の可視化、相談受付 | すべての金融機関連携が保証されるわけではない。(個別確認が必要) |
補足:任意後見は身上監護(入退院や施設入所の契約など)を担える一方、家族信託は財産管理・承継が主目的。家族が役割が異なるため併用を検討する余地はあります。
料金体系と費用の構造
まず、「どれくらいの費用ががかかるのか」一番気になるところではないかと思います。
そこで、取り寄せた資料の説明や経験に基づき、こういう場合でおそらく大体これくらいかな?という相場感を予測してみました。もちろん、家族信託契約をどのような設計にするのかによって異なるため、個別の見積もりが必要です。あくまでも予測ということを前提に、ご参考になさってください。
どれくらいの財産額から契約できる?
まず、公式に表示がある最低価格は以下の通りです。
税込最低価格55,000円〜
家族信託組成のサポート費用
税込2,728円〜
専門家への相談・アプリの利用料
費用の仕組みをもう少し詳しく確認してみましょう。初期費用の家族信託組成のサポート費用は「信託財産額の1.1%」で、その他以下の通り実費が必要となっています。
信託財産の1.1%がコンサルティング料で、最低価格は55,000円ということですから、信託財産への組み入れ金額の最低ラインは500万円ということのようです。さらに信託契約書作成の弁護士報酬と公証人手数料合わせて8万円〜10万円くらいが実費としてかかるとすると、500万円の金銭信託で14万円〜16万円前後が実質の初期費用といったところではないかと推測できます。(不動産は信託せず、登記費用が0円と仮定)
一般的な家庭でよくありそうなケース
金銭の信託
さらに資料によると、一般的なご家庭で金銭を信託した場合の例が出ており、おおよその初期費用が約30〜60万円とされています。
これが弁護士報酬や公証人手数料も含むものとして、コンサルティング料が信託財産の1.1%ということからざっくり逆算すると、2,000〜4,000万円前後の金銭を信託財産に組み入れるご家庭が一般的なのでしょう。
金銭+不動産の信託
さらに、金銭1,000〜2,000万円と、自宅不動産を信託財産とする仮定で考えてみましょう。割とよくありそうなケースです。自宅の評価を仮に3,500万円(土地:3,000万円 建物:500万円)としましょう。合計4,500〜5,500万円ですから、コンサルティング料が50〜60万円。また、公証人手数料も財産額に応じて上がりますので、契約書作成の弁護士報酬と合わせて12〜15万円前後といったところでしょう。さらに、登記費用として15〜20万円程を見込むものとします。すると、最終的には80万〜100万円前後の初期費用がかかってくる計算です。
高いと考えるか?それだけの価値があると考えるか?
決して安いとは言えない料金ですが、親の財産管理という行為に法的な正当性と安心感を与えられる点は、大きな価値だと言えます。相続相談の現場でも同様の提案をすることがありますが、やはり初期費用の金額に驚き、導入を見送る方は少なくありません。価値を感じていただけないのは、わたしの説明力不足という反省もありますが、背景には法律に関する基礎知識や金融リテラシーの不足もあるように感じます。今後少しずつ変わっていくよう願っています。
\うちの場合、費用はどれくらい?/
※広告を含みます。条件・料金は必ず公式で確認してください。
相談〜設定までの流れ(5ステップ)
ここからは、相談から運用開始までのステップをざっくりご説明します。
- ヒアリング(目的・家族構成・財産の棚卸し)
- 設計案(受託者・受益者・信託財産・権限の設計)
- 契約書作成/公正証書化(実費は別)
- 口座・登記等の手続き
- 運用・相談(アプリで可視化/必要に応じ見直し)
それでは、ひとつずつ解説していきます。
1.ヒアリング
「おやとこ」は、個別相談が無料で提供されています。ちょっと緊張するとは思いますが、正直これを利用しない手はないです。
その際、「何もわかりません」と丸腰で臨んでももちろん問題はありませんが、事前に問題整理をしてから臨まれると、より有益な相談会となると思います。この記事にある事前チェックリストもぜひ活用してみてください。
2.設計案作成
まず、信託契約にあたって、委託者(親)と受託者(子)が十分に契約内容を理解する必要があります。また、受託者以外の子達とも情報を共有しながら、全員参加で進めることが理想です。「例えばこんなケースに対して対策可能か?」といったことや、「それによって、不利益を被る(家族関係がこじれる要因になりうる、税負担が増えるなど)可能性はないか?」など見落としのないように、少しでも疑問に思ったことは質問して確認するようにしましょう。また、この段階で任意後見契約と遺言もセットで検討するのもお勧めです。
3.公正証書作成
設計に基づいて作成した家族信託契約書を、公正役場で公正証書にします。親御様が介護施設や病院にいらっしゃり、外出が難しい場合は施設や病院に出向いてお手続きすることも可能です。
4.口座・登記等の手続き
不動産がある場合、司法書士が受託者の名義に変更する手続きを行い、信託目録を登記します。銀行や証券会社の信託口口座を開設し、信託財産を移管する手続きが必要です。(実際には、3.公正証書作成より前の段階で、契約内容の擦り合わせが必要な金融機関が多いのではないかと思います。)
5.運用・相談
おやとこの大きな強みは、アプリによる財産管理や収支把握の自動化にあります。例えば長男が受託者になっている場合でも、次男をはじめ家族が同時に財産状況を確認できるしくみとなっており、家族内での情報の透明性が担保されます。
\家族信託契約は おやとこ で/
※広告を含みます。条件・料金は必ず公式で確認してください。
家族信託に向き/不向きはある?
家族信託の利用自体、向いている人/向かない人というのは確かにあります。以下に主なケースをまとめました。
| 向いているケース | 備考 |
| 収益物件を所有している | 賃料の収納や物件の管理、賃貸契約などの仕事を委託することができます |
| 自宅不動産を売却する可能性がある | 例えば施設に入居する際、自宅不動産は売却して現金化する必要があるなどのケースに有効 |
| 配偶者の保有する財産が少ない | 例えば父と契約した信託財産を、父が亡くなった後に母のために管理・運用できるようにする設計も可能(受益者連続型) |
| 詐欺被害に遭わないか心配 | 契約後は受託者が管理・運用することで、せっかく苦労して貯めたお金を失うリスク |
当面使用しないお金を、一旦子供に託して守るとか、
| 向いていないケース | 備考 |
| 預貯金は少ないが、年金で十分に生活できている | 年金は信託財産に組み込むことができません |
| 主に身上看護(入退院、施設契約)を任せたい | 身上看護は家族信託の趣旨ではありません ※実務上家族なら手続き可能な場合も多いようです |
上記に当てはまる場合は財産管理委任契約・任意後見契約が有効です。親世代ですと、預貯金は少なくても、年金は多いので困っていないというかたは意外といらっしゃいます。しかし、残念ながら年金は信託できません。これが、家族信託契約をするかたにも、任意後見契約と遺言をセットでお勧めする理由でもあります。
個別ケースにおけるアドバイス
「うちの場合はどうなんだろう?」「おやとこはうちのケースに合っているかな?」ということが気になるところだと思います。個別ケースの相談はやはり一度無料相談を受けてみるのが一番です。とは言え、「詳しくは無料相談で」と言われると身構えてしまいますよね。そのお気持ちはわかります。どうしても心配な場合、「あくまでも選択肢の一つとして検討中」との旨を伝えた上でお話を進められたら良いかと思います。
よくある質問(公式の資料より抜粋)
公式の資料にあるFAQ(よくある質問)からいくつか抜粋したので確認してみましょう。
- 家族信託の相談は無料ですか?→無料です。
- 土日や夜間の相談も可能ですか?→夜間や土日のご相談も承っております。
- 全国どこでも対応可能ですか?→全国どこでもご対応します。
- 家族信託はいつ始めるべきでしょうか?→完全に認知症になられた後ではできません。
- 親の物忘れが多くなってきました。この状況で家族信託はできますか?→ご本人が、名前・生年月日・住所を口述し、契約の趣旨がしっかりとご理解いただける状態であれば、家族信託できるケースもあります。
出典:おやとこ公式資料(2025年8月確認)
相談は、全国で無料で対応。お仕事で忙しい方にも夜間・土日対応ありとのことで助かります。
ここに「いつ始めるべきか?」という問いがありますが、これはわたしからも声を大にして言いたいです。
「まだ元気だし、早いんじゃない?』と思っている状態の時に進めるのがちょうどいいくらいです。骨折して入院したら、急に様子が変わってしまった、なんてことがよくあるからです。
Q&Aでも「本人が名前・生年月日・住所を口述し、契約の趣旨を理解していれば契約できるケースもある」と書かれています。ですが、この“理解している状態”は一度失われると取り戻せません。迷っている間に機会を逃すことがないよう、早めの判断が大切です。
おやとこ の無料相談に行く前に
公式の資料によると、「初回相談では親の財産状況を把握していない段階でも大丈夫。大まかな財産状況をもとにお話し進めますよ。」とのことです。とは言え、せっかくの個別相談の機会です。より具体的な話を進めるためには、やはり確認事項を事前に洗い出しておくことをお勧めします。
申し込み前チェックリスト(保存版)
以下のような項目(ご自身の考えや把握できている現状)を簡単にでも整理しておきましょう。チェックリストのPDFでご用意したので、記載例を参考に準備してみてください。
- 目的や希望(何を守り、何を避けたいか)
- 違う意見・考え方を持つ家族はいないか?いる場合、誰がどのような考え方なのか?
- 家族構成(居住地や婚姻関係など)
- 財産の棚卸し(銀行名・証券会社名・不動産の所在)
- 確認しておきたいこと(費用内訳、追加費用のかかる条件、受託者の候補、権限の範囲など)
\ダウンロードしてご利用ください/
\家族信託契約は おやとこ で/
※広告を含みます。条件・料金は必ず公式で確認してください。