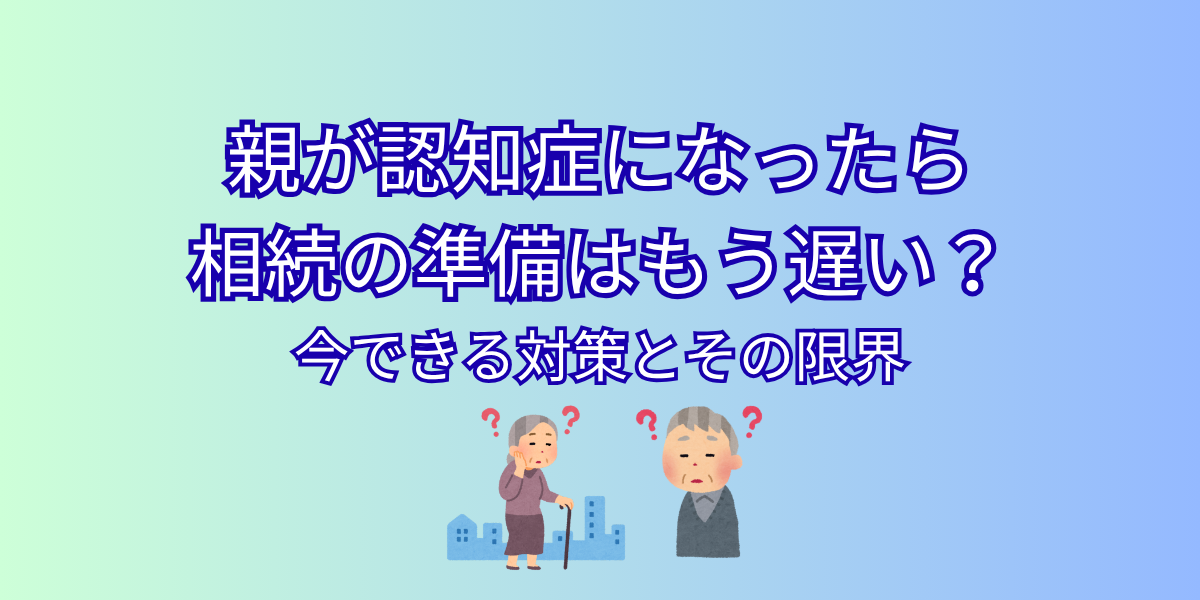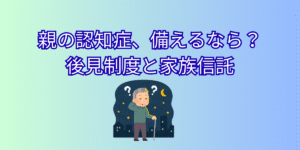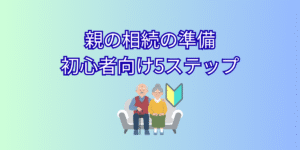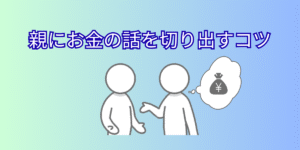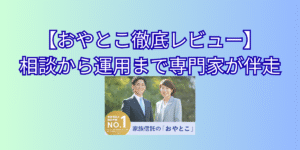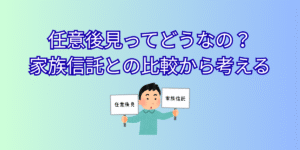「親が認知症」と言っても、症状の出かたや進み具合は人によってまちまちです。
診断が下ったら全てが手遅れ、と一概には言い切れないものです。
とは言え、相続や財産管理の準備は “まだ元気なうち”しかできない ことが多いのも事実です。
「親が最近、同じ話を繰り返すようになった。」
──そんな時には、一抹の不安がよぎるもの。
「でも、まだ体は健康で元気だし…。」
「子供の方からは、切り出しにくい話だし…。」
──と話を先送りしてしまっていませんか。
この記事では、親が認知症になってからできなくなること・できること、そして「今」やっておくべき備えを、わかりやすく整理します。相続準備に早すぎるということはありません。
認知症になると相続準備はなぜ難しくなるの?
判断能力を失うと契約や遺言が作成できなくなる
冒頭に述べたように、症状の出かたや進み具合は人によってまちまちです。
例えば、明晰な時とそうでない時がまだら、というようなかたもいらっしゃいます。
この場合、状態の良いタイミングであれば、手続きが進む可能性もあります。
当てはまる場合は、一度専門家に相談をしてみるのも良いかと思います。
しかし、認知症が進行すると「判断能力がない」とみなされます。
この状態になると、本人名義の財産について法律上の手続きはできなくなります。
たとえば、
- 不動産の名義変更(贈与や売買)
- 生前贈与
- 遺言書の作成
- 家族信託契約の締結
上記のような手続きは、どれも相続対策として定番ですが、いずれも「本人の意思で」行う必要があります。
預金の引き出しや不動産売却も制約される
銀行口座についても、認知症が疑われると
「ご本人の意思確認」が取れない限り、払い戻しや名義変更が難しくなるケースがあります。
また、介護施設への入居資金を作るために「実家を売ろう」としても、
所有者である親が契約できなければ、売却手続きは進みません。
つまり、財産を「守る」ための仕組みを作るには、本人が元気なうちに動く必要があります。
「認知症が進行してしまった…もう遅い」というときにできること
家族が代わりにできる手続きは?
財産は凍結、何もできない。というわけではありません。
ただし、できる手続きは制限付きになります。
代表的なのが「成年後見制度」。
家庭裁判所を通じて後見人を選び、親の財産管理を第三者(または家族)が行う制度です。
ただし後見人は、財産を「維持」することはできても「活用」することは難しく、自由度は低い仕組みと言えます。
また、誰が後見人に選任されるかということについても、家族はコントロールできません。
「成年後見人による財産の使い込み」などという事件がたびたび発生しているのも現実です。
 終活ナビ子
終活ナビ子後見人をされている弁護士からは「真夏にエアコンが壊れたので買い替えたところ、大きな支出に関しては事前に裁判所の許可を取るように注意を受けた」などというお話も聞いたことがあります。
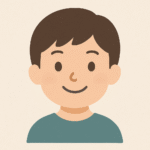
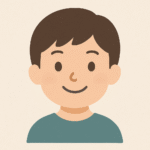
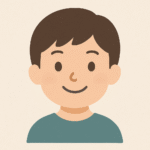
そんな一刻も争うよう状況で、いちいち「事前に裁判所の許可を〜」なんて言っていられないよね。
親身になってくれる後見人がついたとしても、使い勝手が悪いことには変わりないなぁ…。
費用と期間の目安
成年後見人を選任するには、申立書の作成・家庭裁判所審査などを経る必要があります。
この過程におおよそ2〜3か月程度、これらの手続きを専門家に代行してもらえば費用も10万円以上かかってきます。
→【参考ページ】裁判所|後見ポータルサイト
晴れて後見人が選任された後も、後見人報酬として保有財産に応じた負担が毎月発生します。
しかも、基本的には亡くなるまで制度利用をやめることができません。(これについては、近い将来制度改正をされる可能性もありますが、今のところはそのようになっています。)
このように、家族にとっては心理的にも経済的にも、長期的な負担となることを理解しておく必要があります。
→【参考ページ】法務省|成年後見制度・成年後見登記制度Q&A
認知症になる前にできる準備3つ
① 家族信託:柔軟に財産管理できる仕組み
親が元気なうちに、財産の管理や活用を「信頼できる家族」に託す制度です。
たとえば、親が受益者・子が受託者となり、
親の生活費の支払い、不動産の管理、施設費の支出などを子が代わりに行えます。
家族信託は、②で説明する任意後見制度よりも柔軟な制度です。
親の意思を尊重しつつ管理を引き継げる点が特徴。
最近は、家族信託契約の生成に特化したサービスも増えていますので、利用してみるのも良いでしょう。
▼どのようなサービス会社があるの?という方はこちらもチェック!


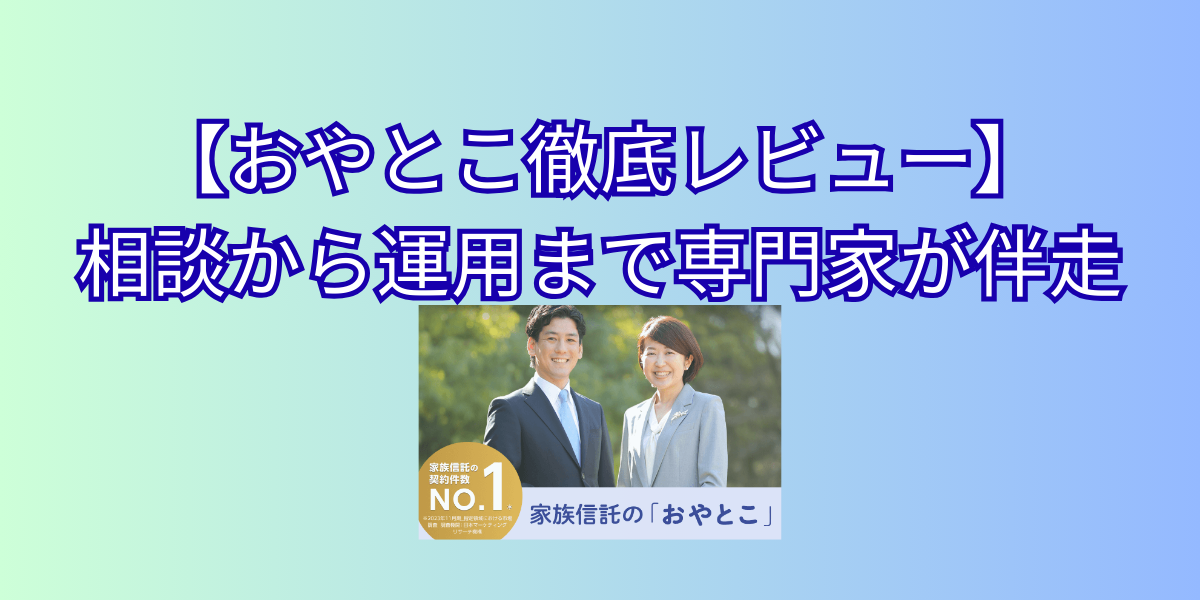
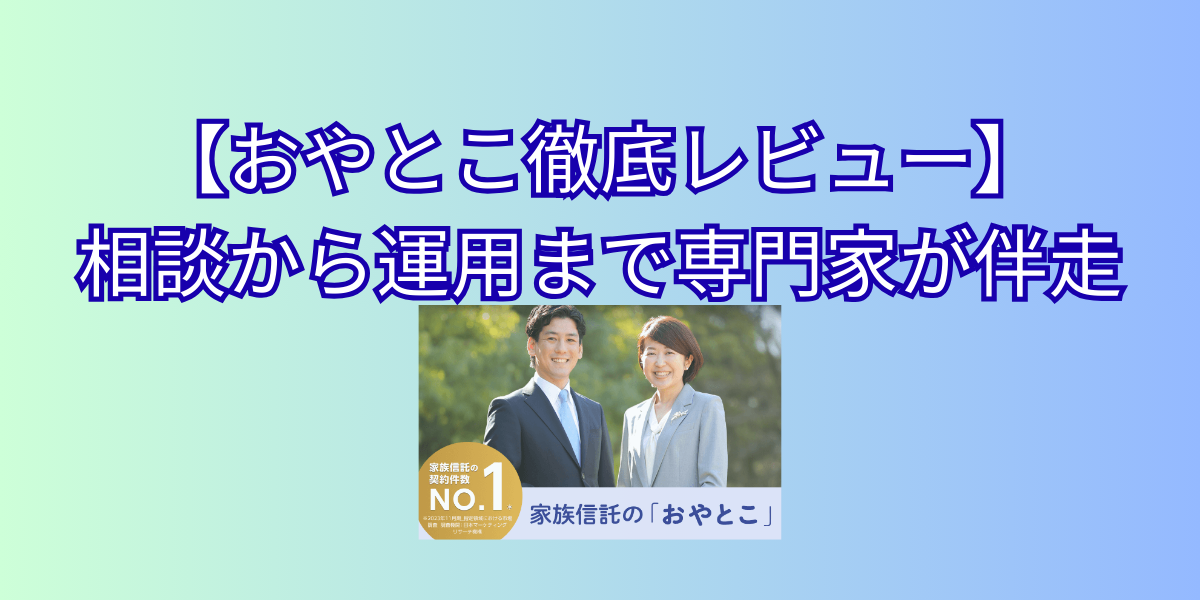
② 任意後見契約:本人の意思を残す制度
元気なうちに「もし判断力が落ちたら、この人に任せたい」と後見人をあらかじめ指定しておく制度です。
法務局への登記が必要ですが、契約時点では効力は発生せず、「発症後」に発動する形になります。
▼もう少し詳しく知りたい方はこちらもどうぞ
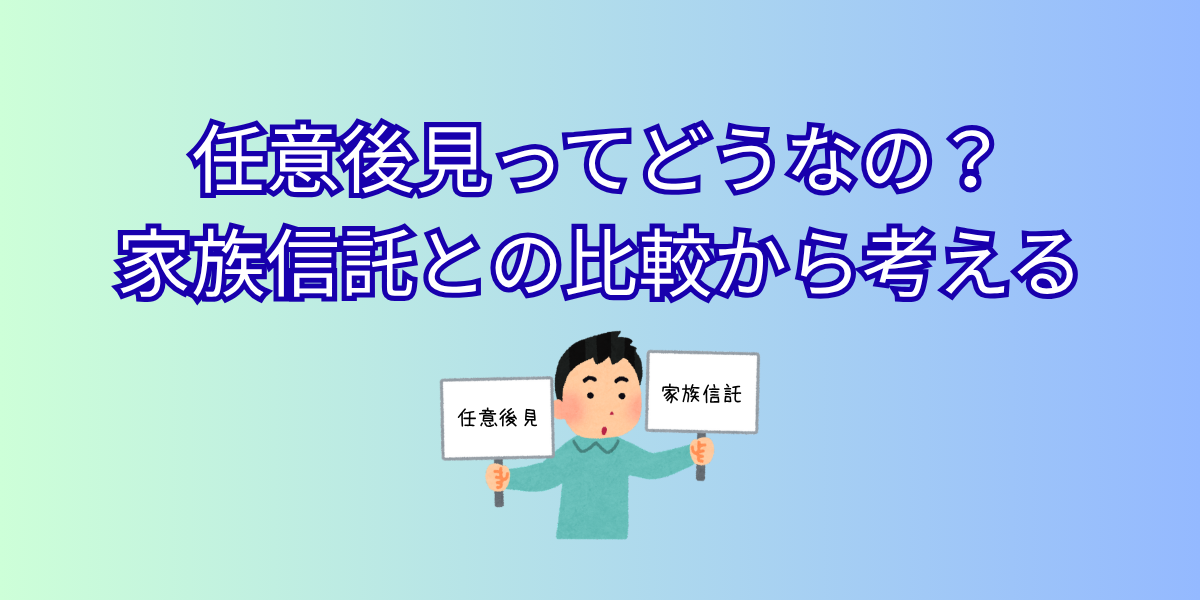
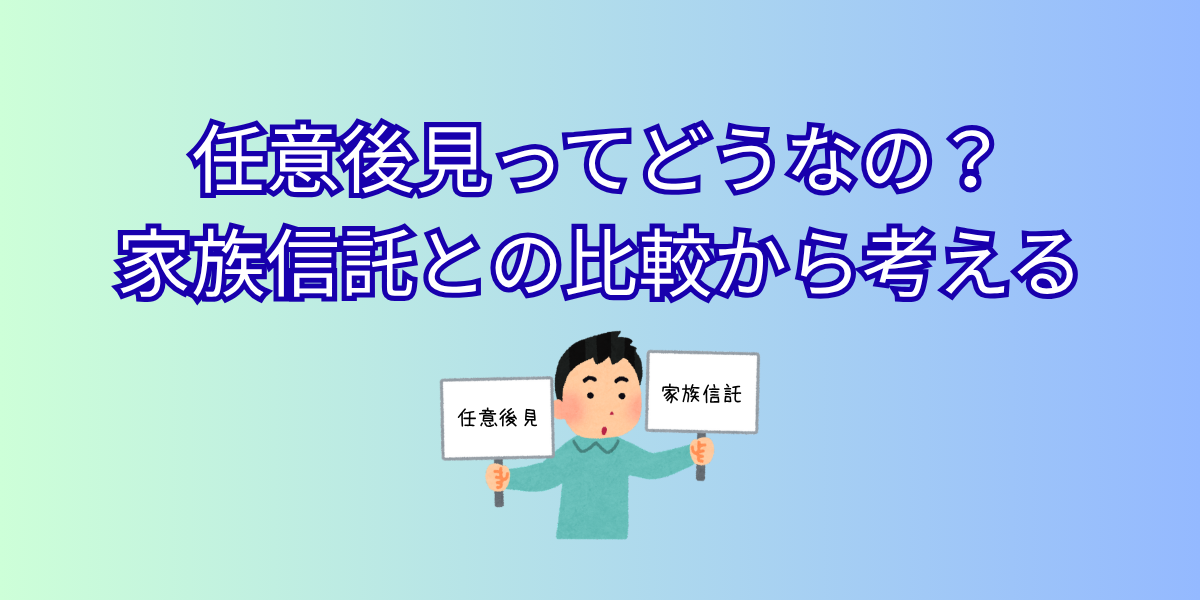
③ 公正証書遺言:判断力があるうちに残す
「この財産はこう分けたい」という意思を明確に残す方法。
認知症が進行すると遺言能力が認められない場合があるため、早めに作成しておくことが重要です。
▼遺言についてはこちらの記事もご確認ください。
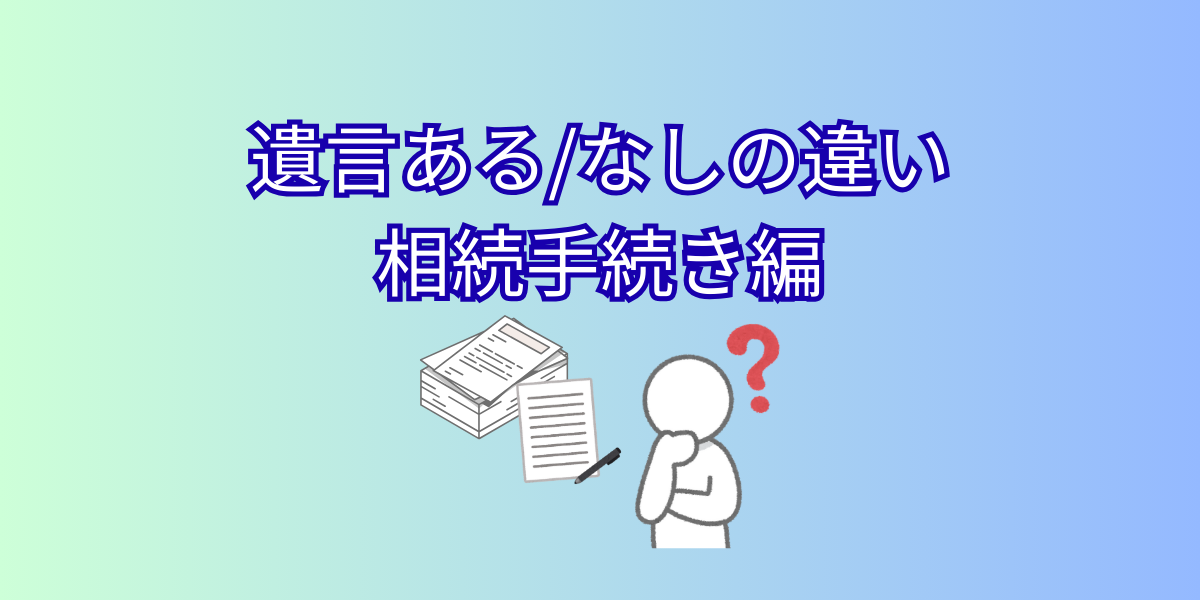
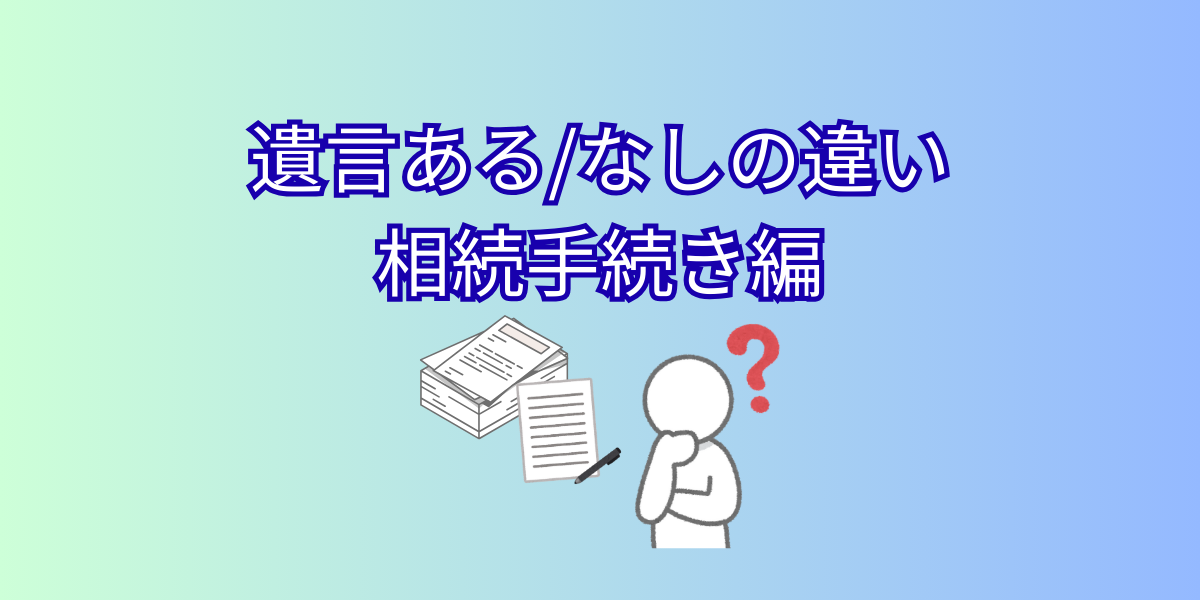
まとめ:迷う前に「話す」「決める」「書く」
「まだ大丈夫」はある日突然「もう遅い」に変わることもあります。
一度判断力を失うと、家族が代わりに準備することはできません。
だからこそ、
- 親と話す
- 誰がどんな役割を担うか決める
- 書類(信託契約・遺言など)に残す
この3ステップを、今のうちに少しずつ進めていきましょう!
▼次に読む:
👉 親が認知症かも?──後見制度と家族信託の違い、備えるならどっち?
👉 親とお金の話、切り出す前に整理しておきたい5つのポイント