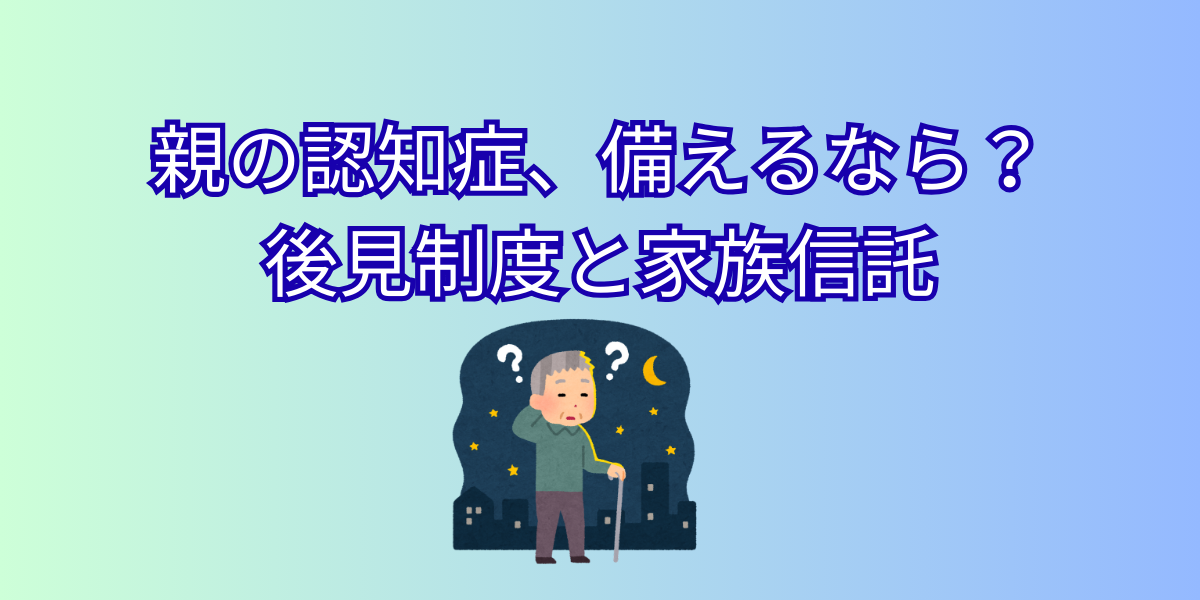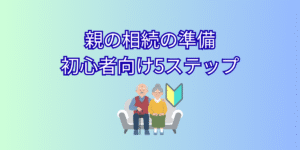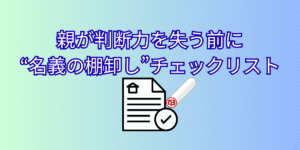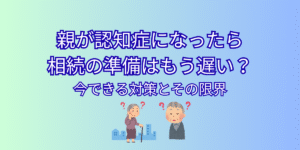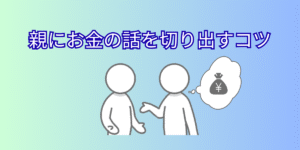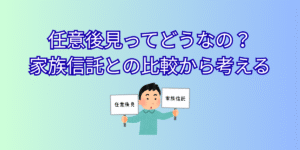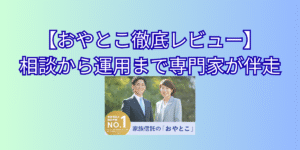後見制度と家族信託──言葉は聞いたことがあっても、何ができるのか、どういうタイミングで必要になるのか、親にはどのように話を切り出したらいいのか…、具体的なことはわからないかたが多いと思います。
自分の親を見ていて、「最近ちょっと物忘れが多いな」と感じたとき、何か備えをしておいた方がいいのか、まだ様子見でいいのか――判断に迷う方も多いでしょう。
いざというときに備える手段としてよく挙げられる「後見制度」や「家族信託」。
でも実はこの2つ、そもそもの性格がまったく違う制度です。
この記事では、親の様子に違和感に気づいたら、知っておきたい備えの選択肢として後見制度と家族信託の違いを徹底比較していきます。
早わかり比較表:後見制度と家族信託、何がどう違う?
まずは、主要な3つの制度をざっくり比較してみましょう。
| 制度 | 主な目的 | 始まる タイミング | 任せられること | 活用のしやすさ・制度の柔軟性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 法定後見 | 被後見人の財産管理と身上監護 | 判断能力が低下してしまった後 | 財産の管理 (制限多め) | △ | 手続きが複雑 |
| 任意後見 | 委任者本人の希望を反映した財産管理と身上監護 | 契約は元気なうちに 発効は将来必要になったとき | 代理権目録を設定することで比較的柔軟に対応可能 | ◯ | やや煩雑 |
| 家族信託 | 委託者の財産の活用を人に託す | 契約は元気なうちに 即効力生じる | 財産の管理 のみでなく 運用・処分も | ◎ | 比較的自由に設計できる |
このように、それぞれの制度は「何を」「いつから」「どこまで」任せられるかに違いがあります。
後見制度と家族信託─その特徴を、利用者目線で比較
ユーザー目線で見たざっくりとした印象を以下にまとめてみました。
法定後見制度
- あくまで「守る」ことに重きが置かれているぶん、自由に財産を動かすことは難しくなります。
- 裁判所が選任するということで、安心な反面、融通が利きにくい印象です。
- 残念ながら、後見人となった専門家による不正の報告も……。(参考ページ:裁判所後見人等による不正事例)
- いずれにしても、後見人を選任するのは裁判所であり、これに不服申立てはできません。この点は、一般の利用者にとって大きな制約になると感じます。
任意後見
- 「元気なうちに契約しておく」という点で、前向きな選択肢と言えます。
- 財産の管理を中心に、契約である程度自由に定められます。
- 任意後見監督人の書面による同意のもと、財産の処分(例えば不動産売却等)も可能と定めておくこともできます。
- 実際に制度が発効するまでには手間がかかる印象です。(参考ページ:裁判所|任意後見監督人選任申立書)
- 「万が一があったとき、最悪の事態を避けるための保険」としては、意義深いと感じます。
家族信託
- 受託者が、財産の管理だけでなく、処分や運用もできるようにあらかじめ設計できます。
- この「運用」まで任せられる、というのは後見制度にはない大きなメリットと感じます。
- 賃貸不動産をお持ちで、管理をこの世代に任せたい場合などには特にオススメできます。
「うちはまだ早い」と思っている家庭ほど、備えが効く
「うちの親はまだ元気だから大丈夫」と思っているうちに、準備をしようとする人は少ないです。しかし、ひとたび判断能力が低下してしまうと、残念ながら契約はできず、選択肢の幅は狭くなってしまいます。
家族信託は、本人の意思がはっきりしているうちでなければ契約できません。もちろん、任意後見も同様です。
「まだ大丈夫」な今だからこそ備えることができます。
もし、「ちょっと不安」と感じ始めているなら、それは準備できるラストチャンスかもしれないのです。
認知症の「はじまりサイン」に気づくには?
医師の診断が出るより前に、家族が「ちょっと変だな」と気づく瞬間はよくあります。
たとえば:
- 同じ話を短時間で繰り返す
- 通帳の管理があやふやになる
- 冷蔵庫に同じ食材が何度も買い込まれている
- 運転や料理のミスが増えた
- 通院を嫌がる
- 人を疑うようになる
こうした変化は本人には自覚しづらく、家族の観察と早めの気づきが大切になります。
家族でやっておきたい備えと対話
実家にひとり暮らしの80代の母を、遠方から支えていたAさん。
最初は「買い物のミスが増えたな」という程度でした。
しかし、ある日、自宅で転倒して骨折してしまい、入院することになりました。
体を動かさなくなったためか、その後、急速に症状が進行していることに気づきました。。
銀行のキャッシュカードは、暗証番号を複数回間違えて使えなくなっていました。
手続きには本人の意思確認が必要と言われ……。
「もうちょっと早く話し合っておけば…」と後悔したそうです。
一方、Bさんは、母の他界後自宅にひとりで暮らす70代の父親を心配し、話し合いを進めました。
自宅不動産と金融財産の一部をBさんに託す、信託契約を事前に交わしていました。
その後施設に入居したため、自宅は処分し、託された財産を父の生活のために捻出するつもりです。
まとめ
認知症のはじまりは、誰にとっても不安なものです。でも、その小さな違和感に気づけたときこそが、「備えを始めるサイン」です。
- 相続準備や財産管理を委任する契約は、元気なうちだからこそできることです。
- 任意後見契約は将来の認知症リスクに備えるという意味で、良い保険と言えそうです。
- 家族信託などより柔軟な仕組みを活用することで、本人も家族も安心できます。
- 「まだ大丈夫」が「もう遅い」にならないよう、早めの対話と準備が大切です。