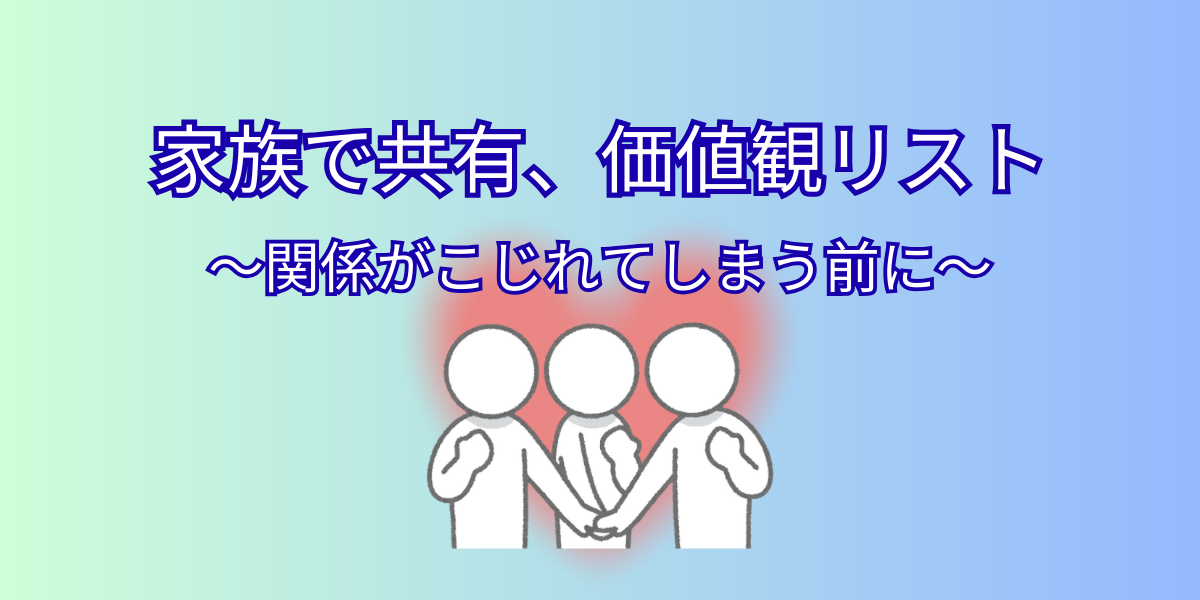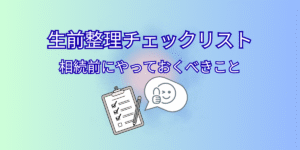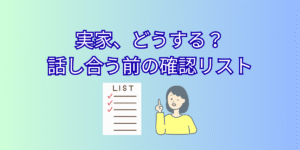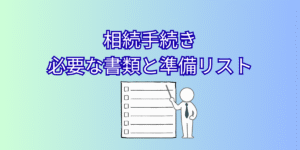家族の仲が悪くなるのは、性格の不一致よりも「価値観のすれ違い」が原因であることが多いものです。
「子どもの頃は、まあまあ仲の良いきょうだいだったのに…。」
「頑固だとは思っていたけど、歳を重ねてますます気難しくなった親に辟易しています…。」
そんな声をよく耳にします。
相続や介護、終末期の選択など――いざというときに家族が対立しないためには、
日常のうちに“ものの見方”を共有しておくことが大切です。
今回は、家族の関係がこじれる前に話しておきたい「価値観のチェックリスト」をまとめました。
はじめに:価値観が共有されていると家族関係の悪化を回避しやすい
知人のお話です。長く延命治療を続けていたお父様がいよいよ危険な状態になったときのことです。ちょうどそのタイミングで、彼女自身が怪我で入院してしまったそうです。
「娘さんの退院までは、なんとか命をつなぎましょう。」医師からはそんな申し出があったといいます。
実際にお父様は数日間を乗り越え、彼女の退院を待つかのようにして旅立たれました。
お父様は数年前に脳梗塞を発症されたとのこと。その後胃ろうの措置を受け、何年もの間、寝たきりのまま生命が維持されていたそうです。そのような姿を見て、「本当にこれでよかったのか」と、答えの出ない思いを抱くこともあったようです。
生命の限界が見えにくくなった今、治療方針の選択には、本人の意思と家族の価値観が深く関わってきます。彼女の体験は、その判断に伴う葛藤や責任の重さを物語っていました。
相続や介護の話題になると、普段は穏やかな家族関係に摩擦が生まれることがあります。その背景には、「前提としている価値観の違い」が潜んでいることが少なくありません。このリストをもとに、家族のあいだで【すれ違い】が起きやすい価値観を、事前に共有してみてください。
お金に関する価値観
「平等」と「公平」の問題は、とても複雑です。
法定相続分が最も公平だと考える人は少なくありません。
でも、それは本当に「公平」なのでしょうか?
たとえば、親の介護を長年ひとりで担ってきた長女と、ほとんど顔を出さなかった長男。
同じ割合で財産を相続することに、納得感はあるでしょうか?(長男は遠方に住んでいた、などの事情はひとまず置いておくとして。)
また、子どものいない夫婦の場合、
残された配偶者が義父母や義兄弟姉妹と遺産を分け合うことになります。
このとき、法定相続分どおりの分け方に、本当の「公平さ」はあるのでしょうか?
- 親のお金は誰がどのように管理するのが自然だと思っているか
- 自分のお金と親のお金を明確に分けて考えているか
- 介護や支援にかかる費用を兄弟でどう分担すべきと考えているか
- 遺産の分け方について「平等」と「公平」をどう捉えているか
 終活ナビ子
終活ナビ子兄弟間で価値観が食い違うケースは、本当に数えきれないほどあります。
なかでも、親の介護をめぐる問題は、感情のもつれを深めてしまう原因になりやすく、特にトラブルが起こりやすいように感じます。
介護・看取りに関する価値観
できれば住み慣れた家で最期まで――そう願う方は多いです。しかし、実際にそれを支える側には大きな負担がかかるもの。在宅か施設か、延命を望むかどうか。本人の思いだけでなく、介護する側の体力・経済的負担・医療面での安心感も含めて、無理のない形を家族で探ることが大切です。
- 在宅介護と施設介護のどちらを基本と考えているか
- 介護に手をかけることと、できる範囲で支えること、どちらを重視しているか
- 最期の迎え方に対する希望(延命・自宅・病院など)について話し合えるか
人生観・責任感に関する価値観
「親孝行」や「介護の分担」といったテーマについて、事前に意見調整するとストレスが軽減します。
とはいえ、親が元気なうちは、このような話題は、なかなか現実味をもって話し合えないもの。
そうこうする間に、急に介護が必要になり、結局身近な誰かが責任を担うことになる――そんなケースは多く見られます。不承不承で押しつけられることもあれば、「私がやるしかない」と一人で抱え込むことも…。
本当は、全体を見渡して調整する<上司>のような人がいれば理想的ですが、そうはいかないのが現実。
前もって「それぞれがどう考えているか」を知っておくだけでも、負担の偏りやすれ違いを防ぐ助けになります。
- 「親孝行」の定義は家族内で共有できているか
- 長男/長女としての役割を当然視していないか
- 自分の生活と親の支援をどう両立させるべきだと考えているか
おわりに
価値観のズレは意外に見えにくく、放置すれば、話し合いの大きな障害になりかねません。正解があるわけではないし、無理に意見をそろえる必要もありません。ただ、「違いがある」ということを知っておくだけでも、対話のきっかけを見つけやすくなるかもしれません。