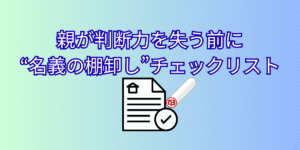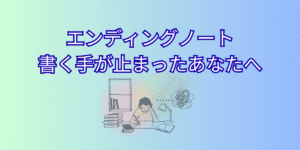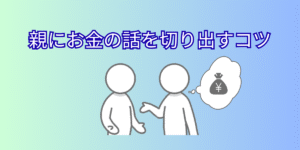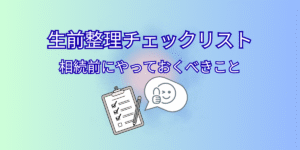はじめに:遺品整理は感情の整理
遺品整理をしていると、それが単にモノを捨てたり、片付ける作業ではないことに気づかされます。
「ときめくかどうかで捨てるか決める」――世界中で話題になったこんまりさんの片付けメソッド。自分の持ち物を整理するには、確かに有効だと感じます。でも、遺品整理においては、この“魔法”がまるで効かないのです。
そもそも、遺品に「ときめき」などほとんどないですから。そこにあるのは亡くなった人の生活の痕跡と、関係性の記憶。「良い思い出」などはあるかもしれないけれど、「ときめき」とは違うかも……。
ということは、合理的に考えれば「全捨て」こそが正解のはず。なのに、父がサッと書いたメモの1枚でさえ、つい手が止まってしまう自分がいる。
もちろん、時間が経てば少しずつ気持ちも整理され、落ち着いていきます。そして、処分できるものも少しずつ増えていきます。けれど、そんな心のペースに合わせていては、片付けは何十年経っても終わらないというのも事実です。
進まない感情の整理と、捨てられない遺品のあいだで
空き家となった実家。誰も住む予定はなく、管理や防犯の面でもできるだけ早く売却するのが理想です。特に過疎地域の家なら、買い手がいるうちに動いた方がいい。実家が空き家になっていると相談を受けたら、客観的な立場から、早めに動くようにアドバイスすると思います。それでも、「今は具体的に考えられない。せめて三回忌までは。」と、気持ちの整理がつかない方も多いです。
亡父の愛車を手放せず、名義変更して維持しているという人もいました。自分自身は運転ができないのに、です。合理的に考えれば、すぐに処分すべきだと分かっているはず。でも、気持ちが追いつかないのでしょう。遺品を見ると浮かんでくる、ほろ苦い感情。あの苦味を、どこかで自ら味わいにいこうとしているような、複雑な感情です。
「実家に行く」意味の変化
かつての「実家」は、帰れば親が出迎えてくれました。独立して実家を離れた後も、帰ると慣れ親しんだ料理があって、気兼ねなく過ごせる場所だったという人が多いでしょう。
また、自宅療養中の親の世話をしに通う時期もありました。大変ではあったけれど、どこか張り合いも感じていた気がします。
けれど、空き家になった実家に行くというのは、まったく別モノ。窓を開けて風を通し、掃除をして、庭の雑草を取る。生きている人の気配がまったくない。一人で淡々と動いていると、虚しさだけが静かに広がっていく──。
遺品整理よりも前に、感情を整理する
こんまり流のような“魔法”が効かない理由は、
遺品整理が「モノの整理」だけでなく「関係の整理」でもあるからかもしれません。
親との関係性、兄弟姉妹との距離感、
亡くなった人への思い、後悔の念――。
そういったものが、押し入れや引き出しの奥からじわじわと湧いてきます。
だからこそ、片付けの負担は心に重くのしかかります。
自分だけで抱えきれないなら、プロの手を借りましょう。
感情に飲まれて動けなくなる前に、片付け業者に依頼すること――。
それもまた、家族間の摩擦を減らすための賢い選択だと思う。
また、片付けていると必ずぶつかるのが、謎のゴミ。
あなたの家にもありませんか?
不燃?可燃?粗大?何ゴミで出せばいいのかわからず、そのままになっている不用品。
そして、素人考えで「これ売れるんじゃない?」と思ってしまうモノ――。
そんな謎のゴミの捨て方も、値段のつく動産かどうかの判断もプロに任せれば安心です。
おわりに
「捨てる?捨てない?」
遺品整理の場面は、コンスタントに「選択」を迫ってきます。
実際、実家の片付けで苦労をした人が、ミニマリズムに目覚めるというパターンも少なくないようです。
親に「もう一度、やり直し!」と言えたらいいのですが……。
今ある自分のモノ、家族との関係、そしてこれからの暮らし――。
亡き親は、何を残したかったのか、誰に託したかったのか。
本来なら去り行く人が決めて、あらかじめ伝えておくべきなのですよね。
わたし自身、自分の最期を誰かに丸投げすることのないよう、自分なりに少しずつ整えていきたいです。