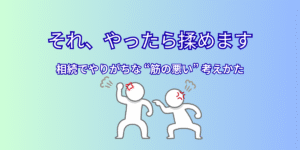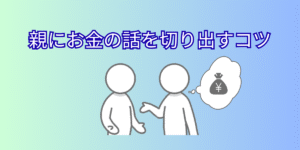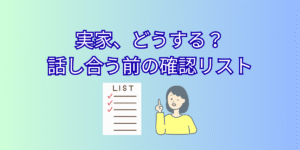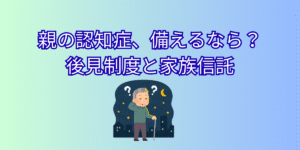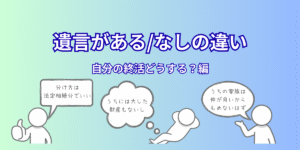実家の相続──それは、親が他界した「あと」の話と思っていませんか?実は、後々のトラブルや後悔を防ぐ一番のポイントがあります。それは、「親がまだ元気なうちに”実家の相続をどうするか”を家族で話し合いの機会を持っておくこと」です。
実家の相続は、お金の問題に感情が絡み合うことにより話し合いが難航しがち。親が元気なうちに方向性を共有しておくことが、後のトラブルを防ぐ最大のポイントです。この記事では、実家の相続でもめないために「いつ」「どのように」「何を」話し合っておくべきか、具体的な手順をご紹介します。
また、もし、すでに相続が始まっていて、「どのように意思決定をしたら良いかわからない」「もっと早く話し合っておけばよかった」と感じている方がいれば──今からできることや見直すべき視点のヒントも、本記事で紹介しています。
この記事でわかること
- あなたもあてはまる?実際にあった、相続でもめやすいケースの具体例
- もめずに決めるための「話し合い5ステップ」
実家の相続についての話し合いで注意すべき点
不動産は「現金」とはまったく違う性質をもつ資産です。そのため、相続の場面では次のような“落とし穴”に注意が必要です。
| 不動産相続で注意すべき点 | なぜ問題になる?補足説明 |
|---|---|
| 分けにくい資産のため、遺産分割でもめやすい | 分けられないからと共有名義にすると、後々トラブルの火種に。 |
| 遺言や事前の話し合いがないと、処分や活用が難しい | 使いたい人、手放したい人の利害がぶつかりやすい。 |
| 評価額と売却価格に差が出ることがある | 相続税は評価額ベースだが、売却は実勢価格で決まる。 |
| 空き家や老朽化物件は“資産”どころか“負債”になることも | 固定資産税の負担や近隣トラブル、倒壊リスクにも注意。 |
| 相続で生活圏が分断されることも | 遠方の実家を管理するストレスや交通費がかさむ。 |
| 相続後も固定資産税や維持管理費がかかり続ける | 「実家は家族の拠点とするために残したい」と思っても、ランニングコストがネックに |
| 状態や立地によって現金化が難しいことも | 売ってお金にして分けることが思うようにいかない。 |
| 不動産にしか使えない相続税の特例がある | 節税とランニングコストのバランスを見極める必要があるが、不確定要素も多い。 |
よくある実家相続トラブルと背景
実家をどうするか──それは、多くの家庭で一度はぶつかる問題です。ここでは、実際にあった3つの事例を通して、見落としがちなポイントやすれ違いが生まれる理由を考えてみましょう。
実家相続トラブルケース1:「残しておきたい気持ち」と「現実的な負担」のはざまで── 誰も住まない実家を“思い出の場所”として維持した結果
 終活ナビ子
終活ナビ子ご両親が亡くなられてから、5年が経つのですね。実家を相続したとのことですが、ごきょうだいはいらっしゃるのですか?



わたしと妹の二人姉妹です。両親が亡くなって、実家は空き家になりました。でも、私はどうしても手放したくなかったんです。あの家には思い出が詰まっていて…。



その気持ち、よくわかります。妹様も同じように感じていましたか?



はい。「家族が集まれる拠点があるのはいいよね」って言ってくれました。でも、あれから5年。掃除や草刈りなどの管理作業は全部わたしがしています。妹には「申し訳ないとは思うけど、実家まで行くだけで2時間位かかるから、なかなか頻繁には足を運べない。」って言われて…。



そうですね。人が住まなくなった家は傷むのが早いですから、お手入れが重要です。庭付きの立派なお家だと、管理のための作業負担も大きくなりますね。



それでも以前はお盆や年末年始などに、お互いの家族全員で実家に集まったりしていました。でも、子どもたちも独り立ちし始め、最近は全員で集まれる機会も減ってきました。今では何のために残しているのかって思うと、正直、しんどくなってきています。



「思い出を残したい気持ち」と「実際に発生する負担」は、時間とともにズレが大きくなります。冷静に見直すタイミングも必要ですね。
感情だけで実家の維持を決めても、お金と手間の分担について曖昧にしておくと、のちのちトラブルになりがちです。思い出を大切にしながらも、維持コストや管理負担を具体的に話し合っておくことが大切です。
実家相続トラブルケース2:介護は“家族の仕事”なのに── 長年支えてきた私には、何も残らなかった
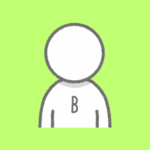
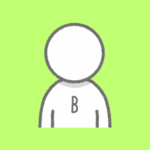
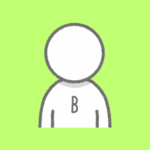
姉と兄とわたしの三人兄弟です。父が亡くなって、実家をどうするかって話になったんです。介護は、ほぼ私ひとりで見てたんですけど……結局、実家は兄に相続ってことになっていて。



「兄に相続ってことになっていて」ということは、お父様は遺言を残されていたのですか?
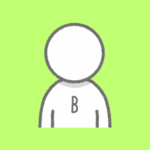
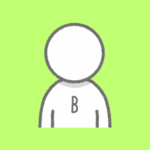
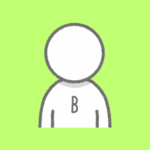
はい。父は「家は男が継ぐものだ」っていう人で……、結婚して家を出た姉とわたしは相続人ではないって考えていたのでしょう。遺言には、財産すべてを長男にって書かれてました。



それはおつらいですね。介護をしてくれたかたへの配慮などは、遺言には触れられていなかったのでしょうか?
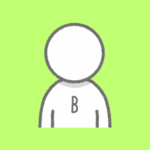
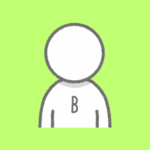
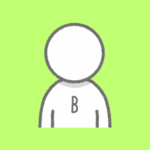
全くありませんでした。わたしが介護していたことも、その時間や費用の負担も、まるでなかったことみたい。



なるほど…。
遺留分侵害額請求権というのをご存知ですか?
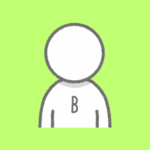
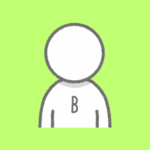
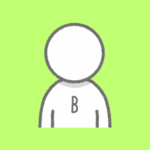
はい。知人に言われて調べました。でも、兄に恨みがあるわけではないんです。それなのに、ちょっとした一言で兄との関係が悪くなるかもしれないと考えると、言い出すのを躊躇してしまいます。それに、お金をもらえれば気が済むという問題でもないですし……。



誰かが担ってきた“見えない苦労”が、評価もされず形にも残らない。
そういうとき、相続って本当に“心”の問題になりますよね。
法律だけでは報われない努力があります。特に介護や看取りなど、見えにくい貢献をどう評価するかは、親自身の認識と遺言にかかっている部分も大きいのです。相続が「感謝のかたち」にならないとき、関係は音もなく崩れてしまいます。
実家相続トラブルケース3:「この家が、他人のものになるの…?」── 血縁へのこだわりと、義家族の居住権が衝突



お兄様が亡くなられて、お子様がいらっしゃらなかったため、相続人がその奥様と妹様であるCさんのお二人になったということですね?
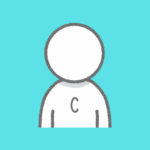
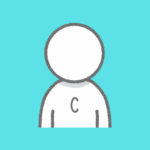
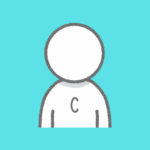
そうです。でも、納得できないんです。あの家は私たち家族の“実家”だったんですよ。それなのに、今後は兄の妻が住み続けることになるなんて…。



もともと義姉さんとは関係がよくなかったのかな…?(ナビ子心の声)
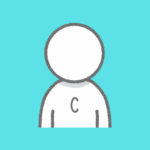
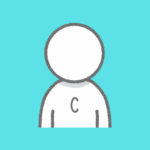
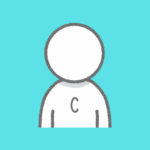
兄に実の子はいませんでした。兄嫁には前夫との間に息子がひとりいますが、兄と養子縁組は結んでいません。その息子が独り立ちしてからの再婚だったので。兄の実子がいるならなんとも思わないですが、「実家が他人の家になった」という感じです…。



なるほど……。
感情の整理は簡単ではないということは、よくわかりました。ただ、法定相続割合で見ても奥様のほうが4分の3と大きいですし、現に居住しているという点でもやはり奥様のほうに有利に働きやすいでしょうね。
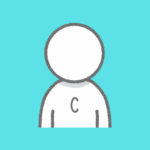
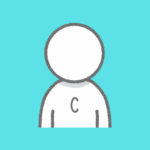
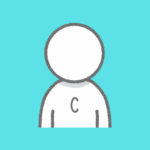
私も「家から出て行ってくれ」とまでは言いません。でも兄嫁が亡くなったら、わたし達の実家が血の繋がりのない他人の手に渡ることになります。それであれば、わたしの息子に継承させたいです。



「実家は私たちのもの」という思いは、金銭だけでは解決しにくい問題ですね。
法律と感情のあいだにある“認識のギャップ”が、家族間の衝突を生むことも。血縁・同居・家族構成などに配慮し、冷静な対話の場を設けることが解決への第一歩です。
実家相続の話し合い、始める前に押さえておきたい5つのポイント
話し合いを円滑に進めるため、実家の相続をめぐって事前に確認しておきたい5つのポイントを整理します。
ここから、詳しく見ていきましょう。
ポイント1:名義・ローン・相続税──実家の“現状”の棚卸し・把握をする
誰が継ぐにせよ、実家の法的・金銭的な「状態」を正しく把握することが必要です。
例えば、名義が亡くなった祖父母のままになっていれば、相続登記手続きは複雑化します。また、ローンが完済されていない場合などには、債務整理の問題が発生することもあります。
- 住宅ローンは残っていないか?
- 土地と建物の名義は誰か?
- 相続税がかかる可能性は?
- 固定資産税はいくらか?
こうした事実確認をせずに話を進めると、後で「こんなはずじゃなかった。」とトラブルになることもあります。
ポイント2:実家に「残す価値」があるかを冷静に見極める
まず話し合いの出発点として、「この実家は残す価値があるのか?」という問いから始めましょう。「価値」とは不動産の価格だけを指すものではありません。もっと「総合的な価値」を考えることが大切です。とは言え、思い出が詰まった家であっても、住む人がいなければ、維持し続けるのは現実的には難しくなります。たとえ愛着があっても“価値ある財産”とは言えないかもしれません。
だからこそ、思い出や感情を大切にしつつも、現実的な判断とのバランスをどう取るかが問われます。誰かが相続して住む、あるいは、賃貸物件として運用するかもしくは、売却するのかを冷静に判断しましょう。放ったらかしにしていると「負動産」になってしまう可能性もあります。感情論は一度横に置いて、総合的な価値を考えることから始めましょう。
ポイント3:「誰が継ぐのか」の考えを親子で共有する
実家を継ぐ人については、親と子の双方の意志をふまえて決めるべきです。「長男だから」「実家に近いから」「親と同居しているから」という理由だけで話が進むと、あとで他のきょうだい達と揉めることになりかねません。
また親自身も「○○が継ぐだろう」と漠然と思っていても、いざ聞いてみると「継ぐつもりはない」と言われることも。このズレを早めに認識しておくことが、後々の衝突を防ぎます。
ポイント4:公平感を意識しつつ、引き継ぎ方を具体化する
実家を引き継ぐ人が、暗黙の了解で決まっている家庭もあるかもしれません。それであっても、他の相続人に対して「不公平感」を抱かせないようにすることが、円満な相続には欠かせません。
たとえば、実家を継ぐ人が相続財産の多くを得ることになる場合、以下のような工夫が必要です。
- 預貯金の配分で調整する
- 生命保険を活用して現金で補う
この段階で、不動産の評価額や現金のバランスだけでなく、「気持ちの納得」を重視することがポイントです。相続は法律だけで割り切れない、人間関係の問題でもあるという意識を持つことで、実行可能な形に落とし込めます。
ポイント5:「いざという時」に向けて準備すべきことを確認する
実家をどうするかの方向性がある程度見えてきたら、「その時」に備えて、遺言書の作成や名義変更の準備を考えておくことが重要です。親の意志が明文化されているかどうかは、残された家族の負担と争いのリスクに直結します。
- 公正証書遺言を作成しておく
- 家族信託などを検討する
- 生前贈与や不動産の名義変更を含めた資産整理を始める
こうした準備はすべて「親が元気なうち」にしかできません。 単に「財産」に向き合うのではなく、「親の人生観や想い」に向き合うことが第一歩です。
実家相続の話し合い、ベストなタイミングとは?
「実家、どうする?」という話題は、とてもセンシティブです。親の老いに向き合うことでもあり、きょうだい間の利害にも関わります。
「今はまだ早い」「まだ大丈夫」と話を先延ばしにしてしまう人も少なくありません。
けれど実際には、“まだ大丈夫なうち”こそがベストタイミングです。以下のような時期や機会を目安に、できるだけ早めに話し合いの場を持ちましょう。
親が元気で判断力があるうちに
話し合いにおいて、親の意思は非常に重要な指針になります。しかし、親が認知症を発症したり、入院して判断力が低下したりすると、意思確認が難しくなってしまいます。親が「まだその気になっていない」段階でも、あえて軽く切り出してみる勇気が必要です。
家族が集まりやすい時期・行事を利用する
きょうだいが離れて暮らしている場合、コミュニケーション不足に陥りがちです。そのような場合はやはり、正月・お盆・法事などの家族の集まりは全員で一度に話ができる絶好の機会になります。これらを活用しない手はありません。
ただし、その場で一気に結論まで求めようとする必要はありません。「今後の方向性を確認する」とか「次回話す機会をつくる」くらいの柔らかいアプローチが理想です。
親の生活環境に変化があったとき
親が高齢になると、「入院した」「免許を返納した」「施設入居の話が出た」などの出来事が起きるようになります。あるいは、「孫が社会人になった」なども、ひとつの節目と言えるでしょう。このようなタイミングも、話を自然に切り出すきっかけになります。「この先、実家をどうしていこうか」という未来の暮らしについて、親の不安や希望を聴くことから始めると、抵抗感も少なくなります。
親が元気なうちに、話し合いを始めるための最適なタイミングやきっかけを探りましょう。年末年始やお盆、法事などの行事や、家族のライフイベント
まとめ:実家相続のトラブルは「事前の対話」で防げる
実家の相続は、「長男だけが継ぐの?」「介護した人が損をするの?」といった感情や不公平感から、思わぬトラブルにつながることがあります。だからこそ、事前に以下のポイントを家族で確認しておくことが大切です。
- 実家に残す価値があるのか?
- 名義・ローン・相続税などの現状把握はできているか?
- 誰が継ぐのか?親の意志は?本人の同意は?
- きょうだい間の不公平感を防ぐことが可能か?
- 親の生前対策として任意後見や家族信託の必要性を検討したか?
- 親の意思を遺言に残すべきか?あるいは相続人同士の話し合いで解決可能か?
話し合いのタイミングは、「親が元気なうち」がベストです。親の生活環境に変化があったときや、お盆・年末年始など家族が集まる機会を利用すれば、自然に話を切り出しやすくなります。“その時”が来てからでは遅いのが相続トラブルです。今こそ、実家と家族の未来について向き合っておきましょう。
相続を「争族」にしないために、今できる対話と準備の大切さをあらためて確認しておきましょう。
現状の把握→親の希望への配慮→子どもたちの事情を踏まえてバランスを取る