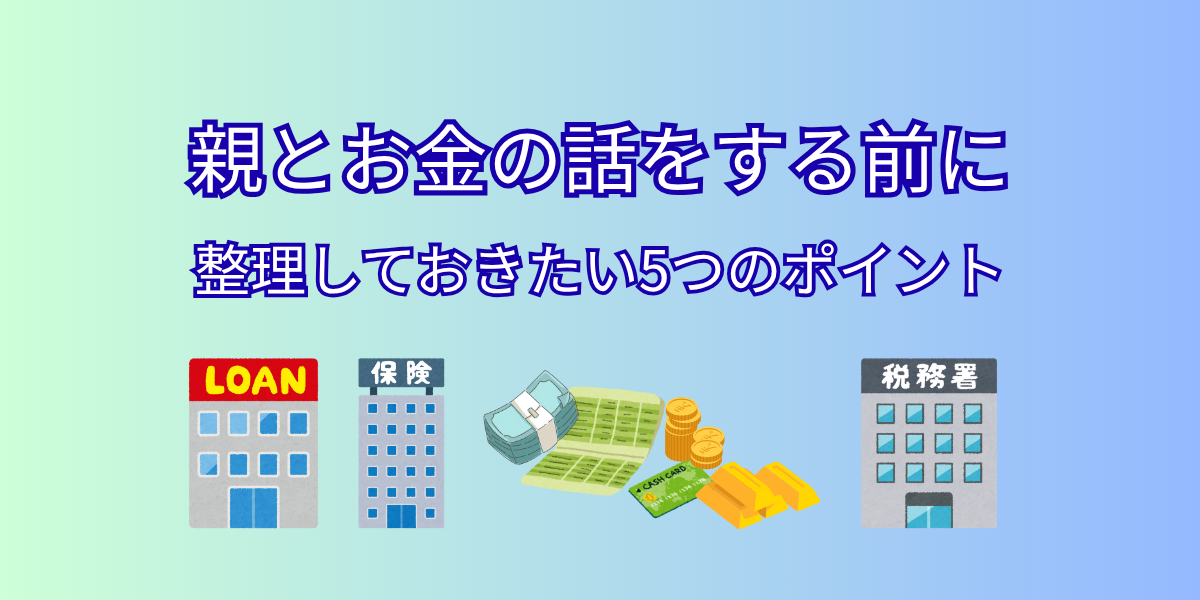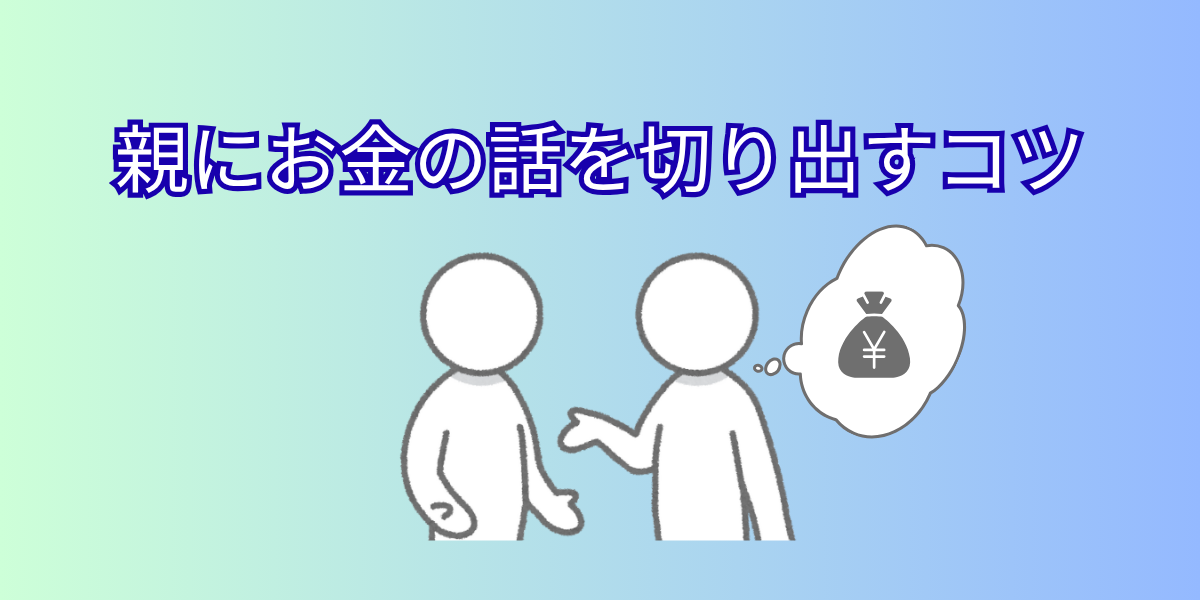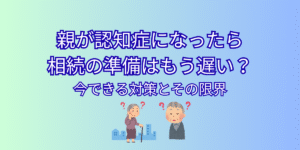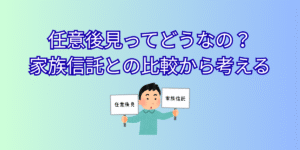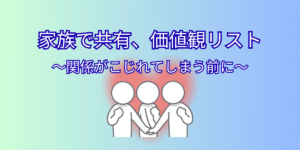「そろそろ親とお金の話をしておかないと」
そうは思っていても、いざ話すとなると躊躇してしまいがちです。
失礼にならないか、嫌な顔をされないか、タイミングはいつがいいか…。
そんな不安がよぎって、結局そのままになっている方も多いのではないでしょうか。
でも実際には、「もっと早く話しておけばよかった」と後悔するケースも少なくありません。
親の体調が急に悪化したとき、介護や相続の準備を進める中で、もっと早く確認しておけばよかった…という声はよく聞かれます。
この記事では、親とお金の話を切り出す前に整理しておきたいポイントを5つに絞ってご紹介します。
相手を思いやりつつも、現実的に話を進めるためのヒントとして、ぜひご活用ください。
聞くべきことが整理できたら、次のステップとして以下の記事もご参考にしてみてください。
1.話す目的をはっきりさせる
介護?相続?生活費?何を知りたいのか、自分の中で整理をつけておく
「なぜ今、親とお金の話をする必要があるのか」
まずはそれを自分の中で明確にしておこう。
たとえば、以下のような目的が考えられる。
今後の介護費用について、あらかじめ一緒に検討しておきたい 。
親の財産状況を把握することで、急な入院や施設入居などの事態に備えたい。
相続時の家族間のトラブルを防ぐため、事前に情報を共有しておきたい。
目的があいまいなまま話を切り出すと、話の焦点が定まらず混乱を招く可能性がある。
親に「なぜそんなことを聞くのか」と不信感を抱かれかねない。
一方で、話す側が目的を明確にしていれば、こちらの誠意も伝わりやすい。
「万一のときに慌てたくないから」という前向きな理由を上手に添えるようにしよう。
- 介護が必要になったときの費用をどうするか話しておきたい
- 緊急時に備えて、どの金融資産がすぐ使えるかを知っておきたい
- 相続時の混乱を避けるため、家族間で情報を共有したい
2.家族構成やお金の流れをざっくり把握しておく
誰が何を負担しているのか、兄弟姉妹との情報共有の可否も確認
親とお金の話をする前に、家族の全体像や現在のお金の流れを、自分なりに整理しておくことが望ましい。
「今、誰がどこに住み、親との関係性はどうか」
「親の生活費はどのように賄われているか」
基本的な情報をあらかじめ把握しておくことで、話が具体的かつ現実的なものになりやすい。
一例として、親の生活は年金収入と自身の貯蓄の取り崩しで成り立っているのか。
それとも子どもからの支援を受けているのか。
はたまた、親から資金援助を受けている子どもがいるのか。
状況によって、話すべき内容や言い回しは大きく変わってくる。
また、兄弟姉妹がいる場合には、関係性や立場も視野に入れておくべきである。
あらかじめ情報共有ができていれば、後々の誤解や対立の防止につながるだろう。
詳細なデータまで調べ上げる必要はない。
話の前提として「ざっくりと全体を見渡しておく」ことをお勧めする。
無用な混乱を避け、要点を押さえた会話につながる。
- 親の収入源(年金/貯蓄/援助)は把握しているか
- 自分または兄弟姉妹が親に援助しているか確認済みか
- 家族間の役割分担や関係性をおおまかに把握しているか
3.「話すこと」そのものへの抵抗を言語化してみる
気まずさ・遠慮・怖さなど、自分側のハードルを認識しておく。
親とお金の話をすることに、漠然とした抵抗感を覚える人は少なくない。
「なんとなく切り出しにくい」
「不躾に思われそうで怖い」
「親子の関係にヒビが入るのでは」
このような感情は、誰にでもある自然な反応である。
そうした感情を押し殺したまま話そうとすると、かえって相手を警戒させてしまう可能性がある。
無意識のうちに遠慮や緊張がにじみ出てしまうのかもしれない。
そこで一度、「自分はなぜこの話題に抵抗を感じているのか」を言葉にして整理してみよう。
「お金の話はタブーという価値観が染みついている」
「親の財産を狙っているのではと警戒されることを恐れている」
自分の内面にあるブレーキの正体は何だろうか?
それを理解することで、冷静に準備を進めることができるようになる。
話題にするのは悪いことではない。
そのように自分が納得できることで、次のステップに進むハードルも自然と下がっていく。
 終活ナビ子
終活ナビ子私も「お金の話は”下品”」という価値観の親の元で育ちました!
なので、お気持ちはよくわかります〜 ^^;
でも実際は「お金の話は”不安を減らす手段のひとつ”」なんですよね。
4.親の立場・世代の価値観に配慮する
「お金のことは心配しなくていい」の背景は?子への配慮や世代間ギャップも
親の立場や世代特有の価値観を理解し、尊重する姿勢も欠かせない。
「お金のことは心配しなくていい。」「自分のことは自分でなんとかする。」
これらの発言の背景を考えてみよう。
子どもに負担をかけたくないという思いや、親としての責任感がにじんでいることが多い。
相続の話をするとお迎えが来る?
また、相続対策のような話題そのものを「不吉」なものと考えている人も少なくない。
親世代であれば特に多いだろう。
年金額や貯蓄額の話などは「下品な話題だ」と感じている場合もあるようだ。
そうした背景を無視して、あまりストレートに問いかけることは避けたい。
「信用されていないのか?」「自分の老いを急かされているのか?」
そのような誤解を生んだり、気分を害されることもあるかもしれない。
大切なのは、相手を問い詰めるのではなく、「一緒に考えていきたい」という立場を取ること。
親の考えや価値観に一度耳を傾けたうえで、こちらの気持ちや心配も率直に伝える。
そうすることで、双方の納得感が得られやすくなる。
- 「老後資金は自分でなんとかするから大丈夫」とよく言う。
- お金の話や遺産の話をすると話題を変えたがる。
- 「相続準備の話なんて縁起でもない」と苦笑いされたことがある。
- 年金や貯蓄の話を「子どもに話す必要はない」と思っている様子がある。
- 「子供に残すほどの財産なんてない」と言っている。
✔️ 複数当てはまる場合・・・
真っ向から否定せず「気を悪くさせない伝え方」を意識して話を進めるよう配慮しよう。
5.話すタイミングと雰囲気に気を配る
急に切り出すのではなく、自然な流れや落ち着いた場面を選ぶ。
内容が正しくても、タイミングや雰囲気を誤れば、親とのお金の話はスムーズに進まない。
逆に、適切な状況さえ整えば、同じ言葉でも受け取られ方が変わってくる。
たとえば、健康診断の結果や身近な人の介護の話が出たときなどは、自然に話を切り出しやすい。
また、芸能人などの相続の話題が取り上げられたときなどにも、話題を広げやすいだろう。
また、「構えずに話せる空気」がつくれるかどうかも重要だ。
家族の集まりの中でも落ち着いて話せる場面、あるいは一対一で向き合える時間が作れると良い。
さらに、「まずは一部だけ」「今回は様子をうかがう程度」といった柔らかな姿勢で臨むことも有効である。
最初からすべてを聞き出そうとせず、何度かに分けて少しずつ進めていくものと考えるべきだ。
話しやすい場面を選び、焦らず段階的に進めていこう。
そうした配慮が、親との対話を長く続けていくための土台となる。
おわりに
親とお金の話をすることは、たとえ家族であっても簡単なことではありません。
しかし、事前に自分の中で目的を整理し、相手への配慮や準備を重ねていけば、思いのほか自然に会話を進められる場合もあります。
本記事で紹介した5つのポイントは、あくまで“話を始めるための地固め”です。
実際に話してみると、思ったより親が前向きに応じてくれるかもしれません。
逆に、今はどうしても難しいと感じることもあるかもしれません。
いずれにしても、これからの家族関係にとって意味のある一歩です。
まずは、自分の不安や迷いを言語化し、少しずつ前に進めていくことから始めましょう。



大きな病気や認知症になってしまうと、打てる解決策の選択範囲が極端に少なくなってしまいます。心構えができたら、少しずつコミュニケーションを取るようにしましょう。