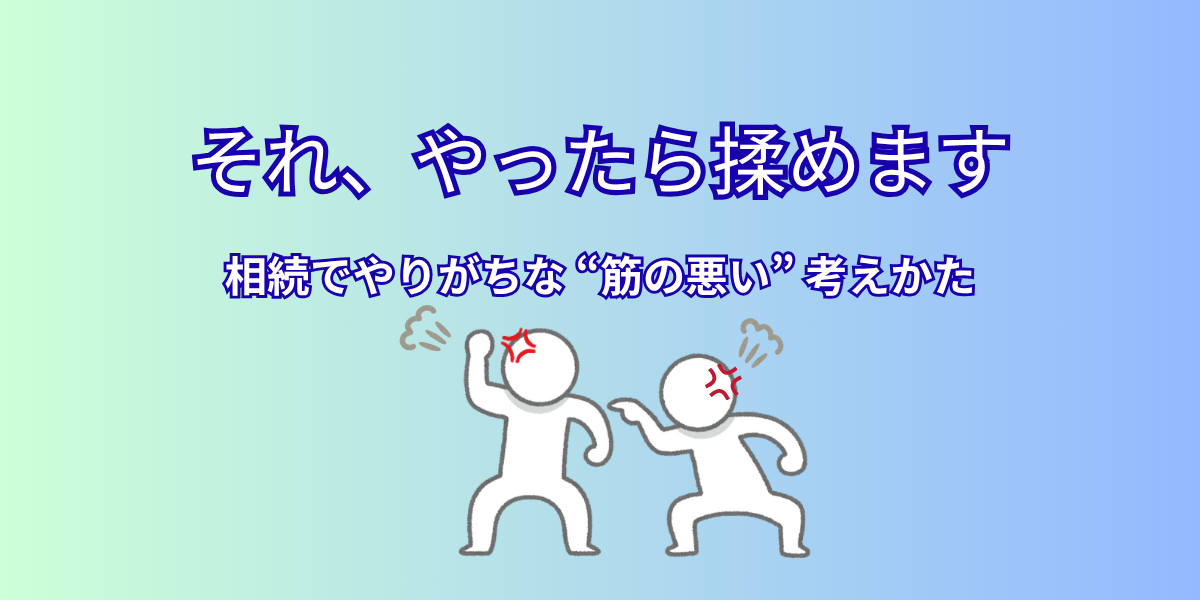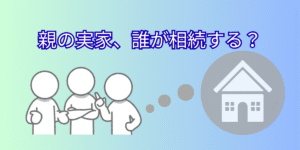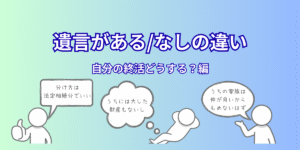親の相続場面において“争族”を避けるために
相続のトラブルは「相手に悪意があったから」だけで起こるわけではありません。「正しいと思ってやったこと」や「思い込み」が原因で、家族同士の信頼にヒビが入ってしまうということは少なくありません。
この記事では、相続の現場でよく見られる“筋の悪い”考え方や行動の例を7つ取り上げます。そして、なぜそれが揉めごとにつながるのか、どのような対策が望ましいのかを解説していきます。
相続税対策ばかりに気を取られる
相続対策=相続税対策(節税)と考える方は少なくありません。
もちろん税金のことは大切です。とはいえ、節税を優先するあまり、「揉めない相続」「家族の気持ちの整理」などが後回しになってしまうのは本末転倒です。
「うちはお金持ちじゃないから、相続の対策なんていらない」
そんな声もよく聞きますが、これは「相続対策=相続税対策=お金持ちの問題」という思い込みから来ているかもしれません。ですが実際には、相続税対策が不要でも、相続対策は必要です。
そもそも、自分が亡くなる時には相続税・贈与税の税制は変わってしまっている可能性も大いにあるということを忘れてはいけません。
法定相続分=最も平等、だと思っている
民法で定められた法定相続分は、たしかに「公平な基準」の一つです。
けれど、現実には家族ごとに事情があり、「平等」と「納得」は必ずしも一致しません。
たとえば、長年介護をしてきた家族や、実家に同居していた人の貢献がまったく考慮されない遺産分割は、かえって不満を生む原因になります。法定相続分は、どうにも分割協議がまとまらない場合のための目安と考えましょう。「気持ちの調整」や「話し合い」を重ねることで、より納得感のある分け方が可能になります。
不動産を共有名義に
これも平等の概念からやってしまいがちなことです。「とりあえず兄弟で共有にしておけば平等」という発想で、不動産を共有名義にしてしまうのにも要注意です。共有は一見フェアに思えますが、売却や修繕、賃貸などの判断が一人ではできなくなるということを意味します。将来的に意見の対立が表面化する可能性も高くなります。
もちろん、共有名義で平等に相続した後、即売却することが可能であれば共有名義も選択肢のひとつです。「即売却することが可能」とは、全員の意見が一致しており、かつ、買い手がつく見込みもあるということです。そうでなければよくよく検討して決めるべきです。
お金のように簡単に分けられない不動産をどのように評価するか。個人の価値観によって異なるため、後々「こんなはずじゃなかった」とトラブルの元になりがちです。
実際にあった事例
親から引き継いだ収益物件を、姉兄弟で共有名義としていたかたのお話です。
物件の管理や税務申告などの実務は親と同居してきた弟が引き継いで行っています。また、姉と兄には年一回収益の分配もしています。しかし、兄の方は弟が不当に多く収入を懐に入れているのでは?と疑念を抱いています。また、ご自身も高齢になり、自分の子供たちに相続で影響が及ぶことを懸念しています。そのため、この物件を売却してお金にしたいと考えるようになりました。が、弟は共同での売却はもちろん、兄の持分を買い取ることも拒否。話し合いは平行線だとのことでした。そうこうするうち、姉の認知症が進行してしまい、とうとう話し合いができない状態となってしまったのでした。
この例のように、共有名義人の一人が認知症になってしまうとどうなるか。成年後見制度などの手続きをしたとしても、当然、売却は非常に困難でしょう。やはり不動産の名義は、将来を見据えた形にしておく方が賢明です。
うちは仲がいいから遺言はいらないと思っている

家族仲が良好なうちは「遺言なんて必要ない」と思いがちです。ですが、人が亡くなると、相続人同士の関係性が大きく変わることも珍しくありません。
両親という一つの「枷」がなくり、生前は遠慮していたことを言い出す人もいます。相続人ではない第三者(配偶者など)の意見が強く影響を与えるケースも非常に多いです。仲が良い家族ほど、関係を壊さないための「道しるべ」として、遺言の存在が大切になるのです。
親の相続の話をするのは失礼、と思い込んでいる
「親の相続の話なんて、縁起でもない。」そう考えて、親の保有する財産を把握する機会を避けてしまう人は多いものです。実際、怒り出す親御様もいらっしゃるようなので難しいところではあります。
しかし、実際の相続発生時に本当に困ることは何かを考えてみてください。「何がどこにあるかわからない」ことの方が大きな混乱を招く原因になるのです。通帳、不動産、保険、借金…これらを把握していなければ対応もできません。
「必要なことを、元気なうちに話しておくこと」は、むしろ誠実な行動です。
本人の気持ちを尊重しつつ、困らないように備えておく姿勢が、結果的に家族全体を守ります。
ネット情報や体験談だけを鵜呑みにする
「知恵袋で見た」「友人はこう言っていた」──インターネットや他人の話は、あくまでその人のケースです。相続は「家庭ごとの事情」が大きく影響します。汎用的なアドバイスだけでは対応しきれません。間違った情報で動いてしまうと、取り返しのつかないミスにつながることもあります。
自治体の無料相談窓口や専門家への相談を活用するのも手です。基本的な知識が身につくと、見えてくる景色がまるで違ってくるはずです。
専門家に相談しない
「相談したら高額な報酬が発生するのでは」と心配して、専門家への相談を躊躇する方もいます。初回の相談は無料としている相談窓口も多く存在しますので、専門家のアドバイスは聞くようにしましょう。
特に、登記・税務・遺言・不動産などの手続きは、間違えると修正が難しくなることもありえます。総合的な視点から助言をしてもらえるような窓口も最近は増えています。相談することで、後々の手間とコストを大幅に削減できる可能性もあります。
「基本的な知識があるが、手続きについてピンポイントで質問事項がある。」そのような場合であれば、税務署や法務局に直接教えてもらうのも良いかと思います。ただし、対面の相談は予約制で時間も短いという場合が多いようですので、質問したいことは事前に明確にしておきましょう。
おわりに
相続は「お金の問題」でもありますが、もっと根本には「人の気持ち」があります。正しい知識と、柔軟な心構えがあれば、防げるトラブルはたくさんあるものです。
相続で「もめないこと」を目指すのではなく、「納得できる形で終えること」を意識する。そんな視点を持てるだけで、相続はずっとラクになります。
この記事で紹介した7つの「筋の悪い考え方」を避けることで、自分自身だけでなく、大切な家族にとっても「後悔の少ない相続」につながる一助になれば幸いです。