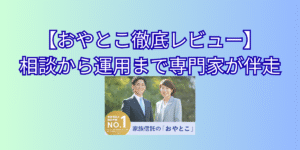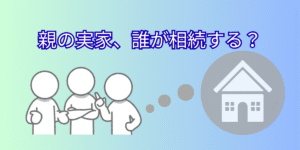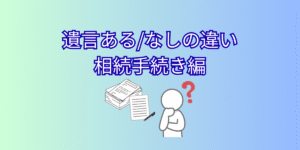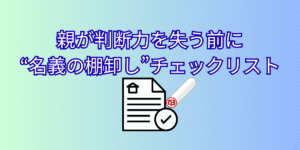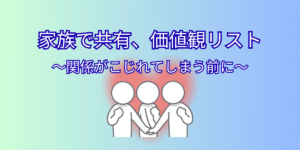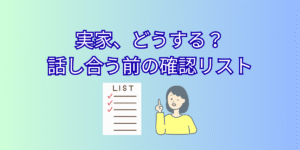この記事では、相続の本質と円満相続のあり方、そして相続トラブルの防ぎ方を、相続相談の現場の経験からお伝えします。
相続相談の現場にいると、さまざまなご家族の事情に触れます。
遺言書の作成、家族信託の組成、保険や贈与など、制度をうまく活用した方も多くいらっしゃいます。
どのケースにも共通して感じることがあります。
それは「相続の本質=円満相続の決め手」は、家族の関係性にあるということです。
だからこそ、円満相続を望むなら、制度よりも“人のつながり”を整えることが大切だと感じます。
制度利用の前に、心のすれ違いの修復を
相続トラブルを回避して円満相続にするには、具体的に何が必要なのでしょうか?
相続でもめる原因は、書類の不備や制度の未利用ではありません。
多くの場合、「言葉にできなかった思い」や「感情のずれ」から生まれます。
たとえば、長男に不動産を託す遺言があっても、次男が「兄ばかり優遇されている」と感じてしまう。
あるいは、親が子のひとりにだけ援助していたことに、他のきょうだいが不信感を抱く。
どちらも、制度としては何も間違っていません。
けれど、心が納得していない状態では、手続きが整っていても関係はこじれてしまいます。
相続を支える3つの土台:「関係」「お金」「制度」
私が現場で感じる“もめない家族”の共通点を挙げるとすれば、この3つです。
- 関係(話せる関係があること)
日常的に感謝や意見を言い合える関係であること。
「家族だから言わなくてもわかる」は、危険な思い込みです。 - お金(最低限の自立があること)
誰かひとりが経済的に困っていると、相続時に不満が噴き出します。
“お金で困っていない家族”は、心の余裕も保ちやすい。 - 制度(話し合いの結果を形にするもの)
遺言や信託は、あくまで話し合いの「結果」。
制度だけ先に整えても、関係が伴わなければ空回りします。
この順番を逆にしてしまうと、
「せっかくの良い制度が家族を壊す」という残念なことが本当に起きてしまうのです。
親自身は「うちは揉めるような子達ではない」と言っていても、いざ両親が他界して兄弟姉妹だけになると関係性がいっき変わることはよくある話です。ぜひもう一度見直してみましょう。
「親しき中にも礼儀あり」が、家族の関係を守る
家族だからこそ、礼儀や感謝の言葉が要ります。
たとえば、
「手伝ってくれてありがとう」
「忙しいのに時間をとってくれて助かった」
そんな一言で空気は変わります。
職場や友人関係に置き換えて考えたら、きっと「そんなの当たり前だ。」と思われるような些細なことです。
そのような小さなことの積み重ねが人間関係を築きます。
相続の準備をめぐって、感情がぶつかりそうなときこそ、ひと呼吸おいて、丁寧に言葉を選ぶことが、最良の防波堤になります。
相続の本質を見誤ると、どんなに制度を整えても円満相続は難しくなります。
また、家族間の信頼が欠けると小さなことから相続トラブルに発展してしまうことも。
“お金で困っていない家族”がもめない理由──円満相続の本質を考える
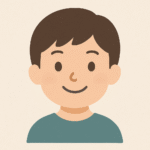 相続しんぺい
相続しんぺいお金を持ってないと、もめやすいってこと?



いえいえ。
確かに、相続トラブルの8割ほどが遺産5000万円以下と言われていたりもしますね。(参考:相続でもめる家族の特徴10選! トラブルを避ける方法や事例も合わせて紹介|相続会議)
でも、ここでいう“お金で困っていない家族”とは、必ずしも”お金持ちの家族”という意味ではありません。
日々の暮らしをそれぞれが自分の力で支え、自分の置かれている状況を人のせいにしなくてもいい…
――そんな精神的・経済的な自立ができている家族のことです。
「相続の争いは金額の問題ではない」とよく言われます。
実際、遺産が数千万円あっても平和な家族もいれば、数百万円で深くこじれてしまう家族もあります。
たとえ裕福でなくてもお金に対する心が安定していれば、「もっとほしい」「不公平だ」とは感じにくくなります。
逆に、誰かが誰かに依存している状態では、わずかな差が不満や疑念に変わりやすくなります。
経済的な自立が心の自立を生み、心の自立が人間関係の安定をつくります。
“もめない相続”は、経済的「豊かさ」ではなく「自立」と「尊重」から始まる。
対話のはじまりは、「確認」ではなく「共有」から
相続の話というと、「財産の確認(=いくらくらい残りそう?)」や「名義の整理(=誰に何を引き継ぐ?)」に終始してしまいがちです。
けれど本当に大切なのは、
「どう生きたいか」「どんな最期を迎えたいか」
という価値観の共有です。
「最近、友人の家で終活の話が出てね」
そんな何気ない一言からでも、会話は始められます。
お金の話よりも、“生き方”の話をしてみましょう。
それぞれが人生で大切にしたいことがあり、それをお互いにできる限り尊重し合うことができている。
それが、もめない家族の共通点です。
“もめない相続”をつくるのは、財産ではなく、価値観を共有できる家族関係です。
相続の本質:円満相続に向けて──“良い関係づくり”こそ最強の対策
遺言も信託も、結局は“信頼”の延長線上にあります。
その信頼は、日々の小さなやり取りの中で育つもの。
家族が、互いに敬意を持ち、思いやりを忘れずに生きていく。
その関係こそが、どんな制度よりも強い、相続の土台になります。